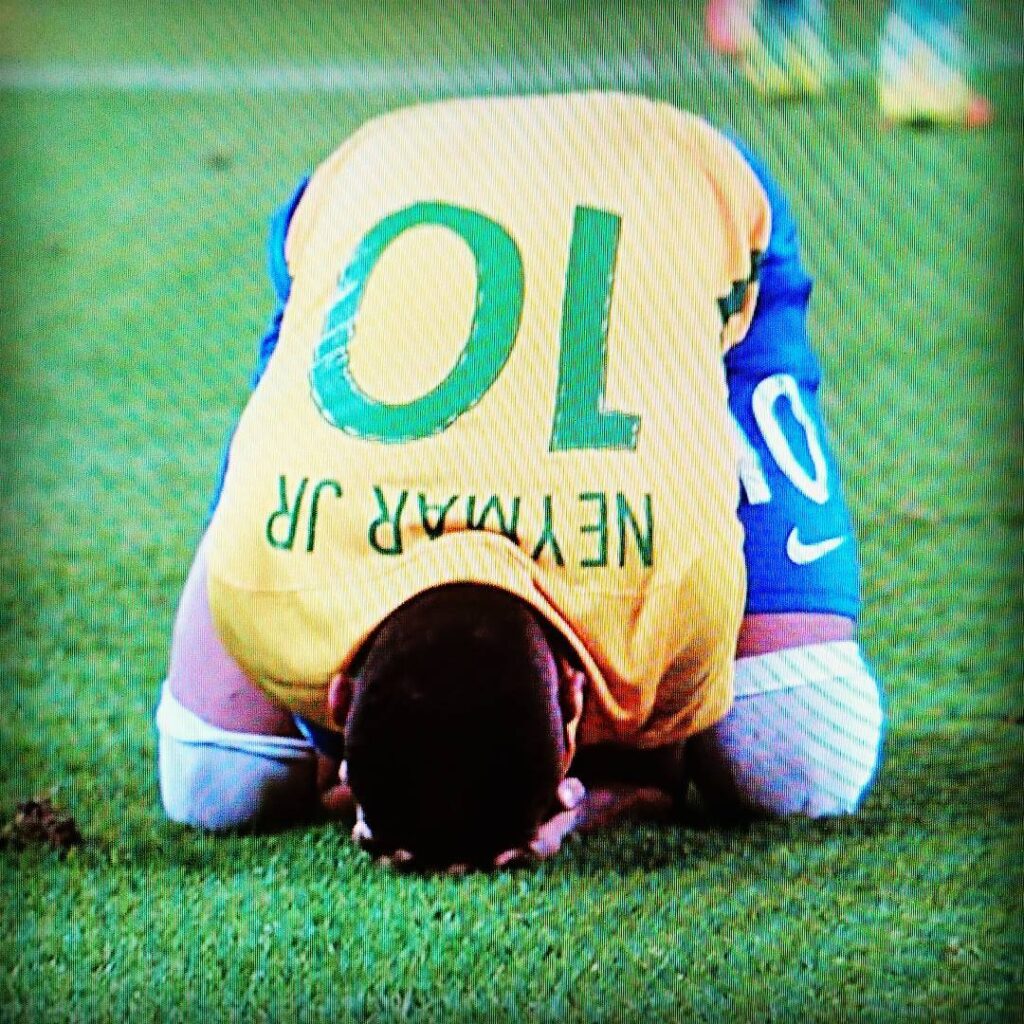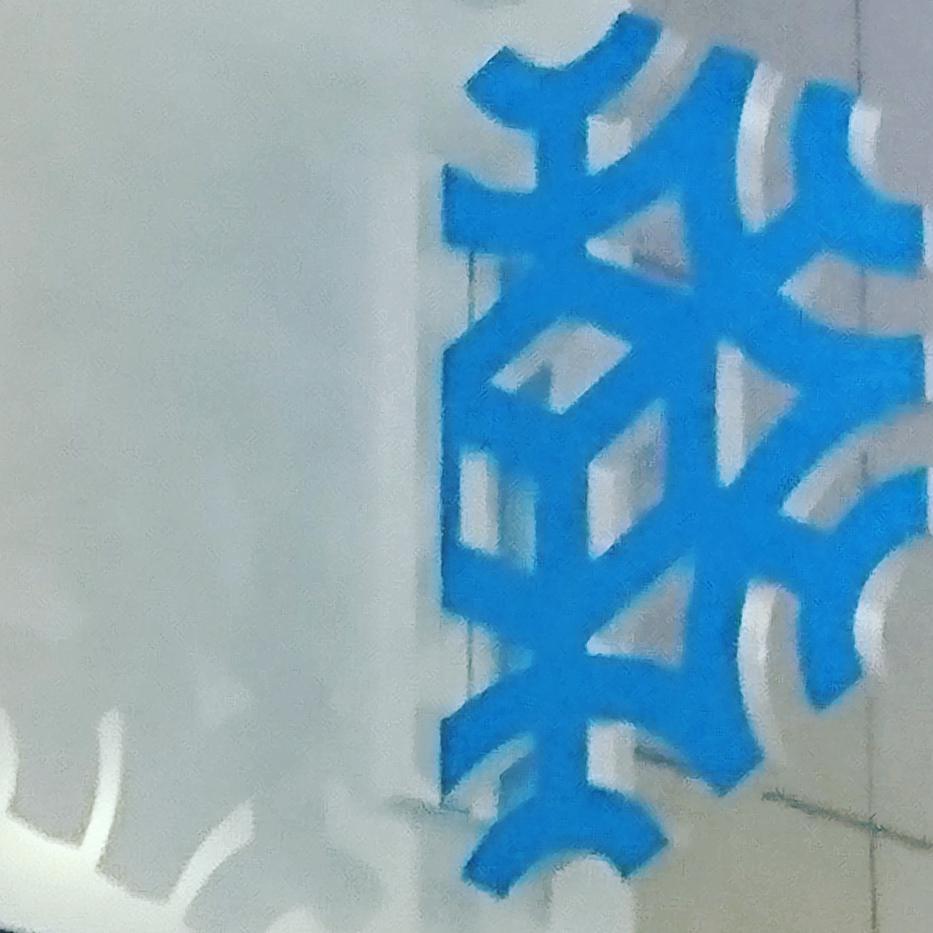W杯の消化不良に、効くのはどれ?
島田雅彦(観戦記)、長嶋有(俳句)、吉本隆明(インタビュー)の3人を除き、以下の14人がエッセイで個性を競っている。
●車谷長吉「空騒ぎ」
「(中田英寿は)実に凶暴そうな、人相の悪い人である。なぜこういう男を広告・宣伝に使うのか」「もう金輪際、キリンビールは飲まない」など企業、資本、広告への「愚痴とぼやき」(by野坂昭如)のオンパレード。
●松尾スズキ「わっしょいわっしょい。がんばれ日本」
「勝っても負けても盛り上がれるんなら、別にサッカーやってなくても盛り上がれるんじゃねえか。つうか盛り上がって行こうよ」
●庄野潤三「ワールドカップ印象記」
妻、長男、次男、孫まで登場し、サッカーより家族。
●保坂和志「天は味方した者にしか試練を与えない」
「これからさき戦争が起こったとしても、新聞の文化面とか社会面で文学者たちが書く文章は、W杯についてみんなが書いている今回の文章程度のものなのだ」
●坪内祐三「非国民の見たワールドカップ」
非国民を気取っていた著者も、いざW杯が始まると徐々に雰囲気に巻き込まれていく。が、「筋金入りの非国民」ナンシー関の死で、再び転向する。
●金石範「W杯のナショナリズム」
「サッカーの勝利に沸く熱狂的な歓声やアクションが即ナショナリズムではないと思う。そこにはいろんな”国”があり、かつて帝国主義国家だった大国もあれば、旧植民地の小国―発展途上国もある」
●陣野俊史「セネガルの『生活』」
フランス文学者らしい、セネガルの勝利に焦点をあてた考察。
●玄月「もっとひねくれろ、日本人サポーター」
韓国がイタリアに勝った直後、新宿・大久保のコリアタウン(著者が韓国人と知られていない場所)でのリアルな反応を取材。
●藤野千夜「ナマW杯の記憶」
サウジアラビアファンの著者は「くじ運はないけれど一日中ずっと電話をかけつづけるだけの暇はあった」ため3試合のチケットを手に入れ、くじ運のいい知人のおかげでもう2試合手に入れたそう。もっともハッピーな観戦記。
●関川夏央「様々な幻想―ワールドカップ決勝戦」
スタジアムでの観戦風景が短編小説風に仕立てられている。面白い。
●野崎歓「蕩尽の果て」
「アルナーチャラム」というインド・タミル語映画の話から始まり、W杯の眩惑的な魔術に言及しつつ「ハレが最終的にケを圧倒するということはありえない」と語る正統派エッセイ。気持ちいい。
●星野智幸「Don’t cry for Argentina,」
「自分の存在をアルゼンチンのフットボールに賭けようとした」と言いつつ「私の態度にはどこかねじれたものがあり、そのねじれは日本のナショナリズムの現れ方に根ざしているということも、気づいている」。自分の存在をイタリアのフットボールに賭けようとした私としては、個人的に共感。
●高橋源一郎「2002 FIFAワールドカップと三浦雅士さん」
話をそらし続ける著者だが、日本におけるW杯の気分を的確に伝えている。
●野坂昭如「サッカーからサッカへ」
「サッカーに、まったく興味がない」という著者の文は、ほかの13人(+3人)と比べて格段に歯切れがよく、プロフェッショナル。読み手が求めているのは、主張の正しさよりも主張の明快さなのだ。
「控えのキーパーだけじゃなく、なんだか人相のよくない、表現大袈裟、鬱屈している感じのプレイヤー皆さん、作家に向いてるんじゃないか。監督は編集者。Wカップも捨てたもんじゃない、観客数万、これが本を買ってくれりゃ、こりゃ、いいぜ。村上龍は判っている、えらい」
2002-07-09