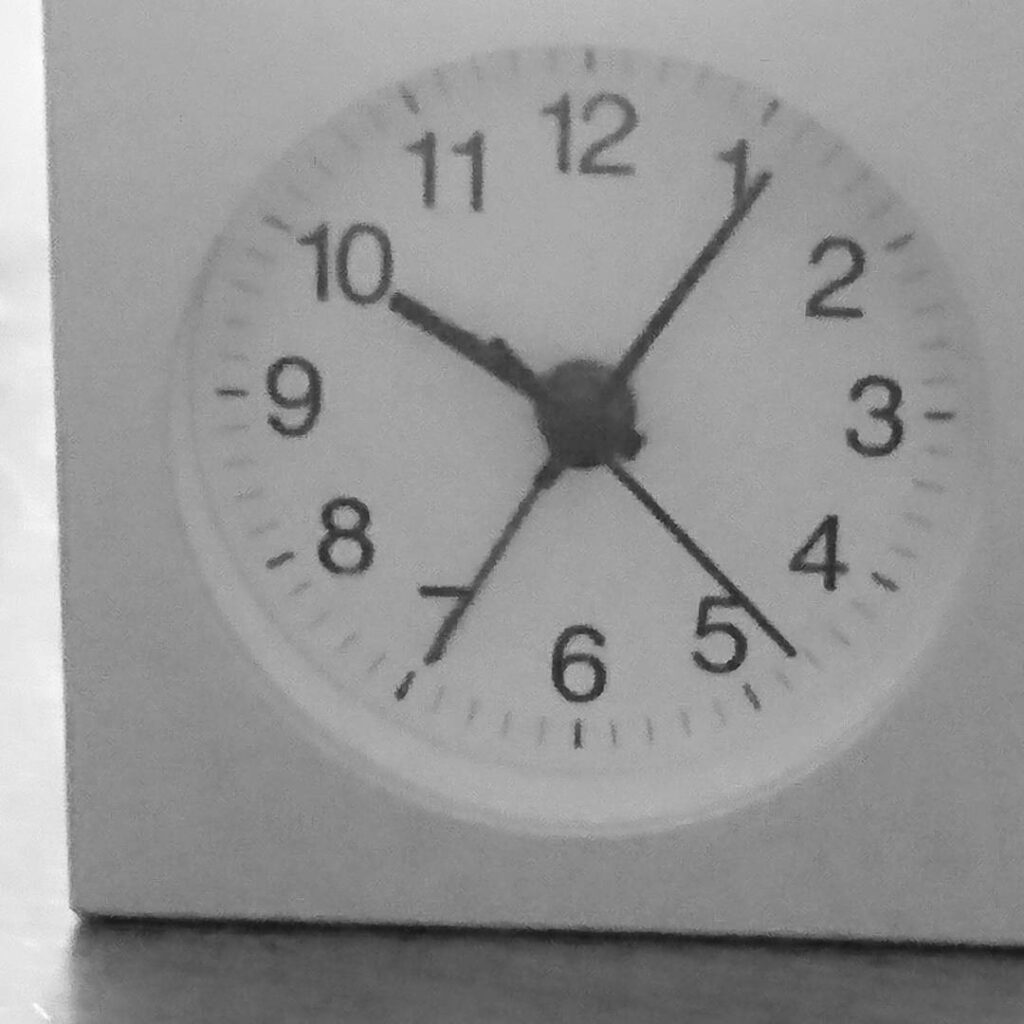愛とブランドとワイン。
アニヴェルセル表参道は、記念日(=アニヴェルセル)をテーマにした複合施設だ。ギフトアイテムやファッション・セレクトショップのほか、イタリアンレストランとウエディング施設があり、オープンカフェは連日大賑わい。チャペルで結婚式を終えたカップルは、このカフェの前を通り、居合わせた人々から一斉に祝福を浴びる。
だが、この地下に、500円で入場できる「もうひとつの教会」があることは、あまり知られていない。経営母体の会社が収集したシャガール・コレクションを展示するアニヴェルセルギャラリーである。
表参道を挟んだ向かいには、グッチ青山店がある。このブランドのブームを再燃させた米国のクリエイティブ・ディレクター、トム・フォードが去り、数日前、社内のデザイナー3人が後継者に決まった。この事件によりブランドのスターシステムは崩壊したともいわれるが、ブランドにとっていちばん大切なものとは何だろう。 創業者? 経営者? 社名? ロゴマーク? 創業者一族? たたき上げの職人? 社内の先鋭チーム? それとも外国から招かれたカリスマデザイナー?
アニヴェルセル表参道の場合は「アニヴェルセル」という1枚の絵である。シャガールが最愛の女性ベラと宙を舞うようなキスをし、心づくしのケーキや花で誕生日を祝う部屋。この絵を見ていると、アニヴェルセル表参道が扱う「おめでたいコトやモノ」には根拠があるのだとわかる。ページェントスタイルのウエディング、100種類以上のシャンパン、ハートをモチーフにしたショコラ、半永久的に美しいプリザーブドフラワー…すべてが愛を大切にし、記念日を祝福する「アニヴェルセル」の精神に基いているのだ。
シャガールは、この絵を2度描いた。ベラと結婚した年でもある1915年版はニューヨーク近代美術館にあり、アニヴェルセルギャラリーにあるのはグッゲンハイム美術館経由で渡ってきた1923年版。幸せの絶頂にあったであろう彼は、散逸してしまった「記念日」をもう一度描き直したのである。が、欲をいえば、この絵には悩みがなさすぎる。シャガールの絵は幻想的なほど面白いのだ。ベラを亡くした後に描かれた「天蓋の花嫁」(1949)は、一緒に暮らし始めた女ヴァージニアを抱きしめているはずなのに、顔の半分がベラになっているというスゴイ絵。その後結婚した3番目の女ヴァヴァによって、長年封印されていたという。
ギャラリーでは数ヶ月に一度、作品の一部を入れ替え、今は版画と詩が展示されている。詩を読むと、シャガールが夢のような絵ばかりを描いていた理由がよくわかる。愛する人の死は、そう簡単に受容できるものじゃない。昨日キスをしたはずの相手が、いま目の前にいないはずがない。シャガールは生涯、空を飛びながらベラを探し続けたのだと思う。
1970年のシャトー・ムートン・ロートシルトのラベルは、シャガールが描いたものだ。私は数年前、26年分のムートンを試飲するというマニアックな企画に参加したが、シャガールラベルのムートンは驚くほど赤みが濃かった。熟成香の強い1973年のピカソラベルや、酸が主張する1975年のウォーホールラベルよりも断然フレッシュだったのだ。奇跡的に酸化が止まり、永遠の余韻を秘めたワイン。それは98歳で亡くなるまで愛を追い、夢を見続けた少年シャガールのマジックだったかもしれない。
ベラが亡くなって60年、シャガールが亡くなってからは19年が経った。2人は天国で再会できただろうか。それは、彼が繰り返し描いた絵のようにロマンチックな光景であるに違いない。
2004-03-17
amazon(Ch.Mouton Rothschild 1970)amazon(Ch.Mouton Rothschild 1973)amazon(Ch.Mouton Rothschild 1975)