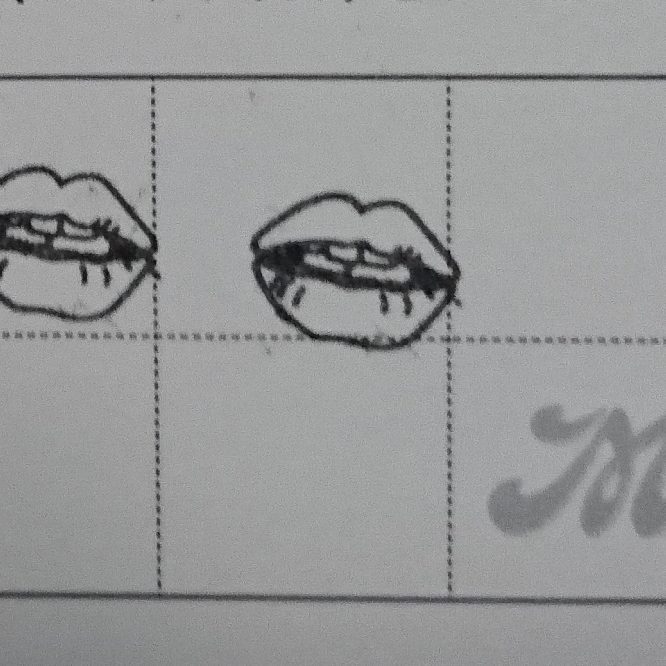表参道 VS モンテナポレオーネ通り。
取材を兼ねて、秋冬コレクション開催中のミラノへ行った。モデルやファッション関係者も多いビジネスの雰囲気は楽しいが、そのうちふと思う。これじゃあ東京にいるのと大して変わらない?
ブランド店が並ぶモンテナポレオーネ通りを歩いても、なんだか表参道を歩いているみたい。今や有名ブランドの多くが表参道近辺に進出し、店を構えているからだ。だけど、圧倒的に違うのは建物。石造りの古い建物が続くモンテナポレオーネ通りには、それだけでシックな風格が感じられる。
一方、表参道はといえば、統一感のない建物が無秩序に並び、我こそが目立て!という感じ。新しい建物が次々にできるから、目立てる期間は短く、エスキス表参道なんて、まだ4年ちょっとなのに解体してしまった。この中のいくつかのブランドは表参道ヒルズに移ったことになるわけだが、来年は、ここにどんな目新しいビルができるんだろう?
だが、東京とミラノの本質的な違いは建物じゃない。世界一のブランド輸入都市、東京とは異なり、ミラノの店はほとんどが自国ブランドで、レストランもカフェもブティックもイタリアン。自国の文化で埋め尽くされているというわけだ。
中心街に近い、流行りのレストランを予約してみたものの、場所がわからなくなってしまった。仕事帰りっぽいミラネーゼに聞いたら「この店をどうして知ったの!? ここは超おいしいわよ。一緒に来て」と案内してくれた。
最近、表参道近辺にもアジア方面からの旅行者が多く、私もよく店の場所を聞かれる。でも「この店をどうして知ったの!?」と驚いたりはしない。プラダもコルソコモもレクレルールも輸入ブランドであり、アジアからのお客様にとっても私にとっても、それらは同じ「異国文化」なのだ。もしも骨董品屋や蕎麦屋の場所を聞かれたら、私だって「この店をどうして知ったの!?」と思わず聞き返してしまうかも。
「LP MAGAZINE」は、イタリアのランジェリーブランドLA PERLAが発行している伊英 2か国語併記の雑誌だ。最新号は高級感のあるシルバーの装丁。春夏ランジェリーの紹介やショーのバックステージ、自社製品のハンドメイドへのこだわりやインテリアに関する記事なんかもある。
中でも興味深いのが、イタリアで暮らすことを選んだ日本人女性アーティストへのインタビュー。イチグチケイコ(漫画家)、スズキミオ(インテリアデザイナー)、スナガワマユミ(シェフ)、オガタルリエ(ソプラノ歌手)の4人に「日本へ持って帰りたいおみやげは何か?」「忘れられない日本の記憶は何か?」などと聞いている。
「日本へ持って帰りたいおみやげ」として彼女たちが挙げたのは、長い休暇、ゆっくり楽しむ食事、安くて美味しい肉や野菜、太陽、活気、温かいイルミネーション、社交場としてのバール、エスプレッソマシーン、生ハム、ワイン、パルミジャーノレジャーノ、など。
一方、「忘れられない日本の記憶」としては、四季、花、温泉、桜、新緑、紅葉、新幹線、効率的なサービス、時間厳守、ストがないこと、など。
イタリアのよさは、ゆとりと活気と食文化。日本のよさは、四季折々の自然の美しさと便利さ。そんなふうにまとめられるだろうか。
イタリア在住35年のソプラノ歌手、オガタルリエさんが「忘れられない日本の記憶」のひとつとして「セミの声」を挙げているのを見て気がついた。
表参道にはけやき並木があり、そのせいで、夏にはセミが鳴く。これらは、石造りの建物が並ぶばかりのモンテナポレオーネ通りには、ないものだ。
表参道ヒルズを低層にし、けやき並木を生かすことを何よりも優先した安藤忠雄は、正しいのだ。
2006-03-10