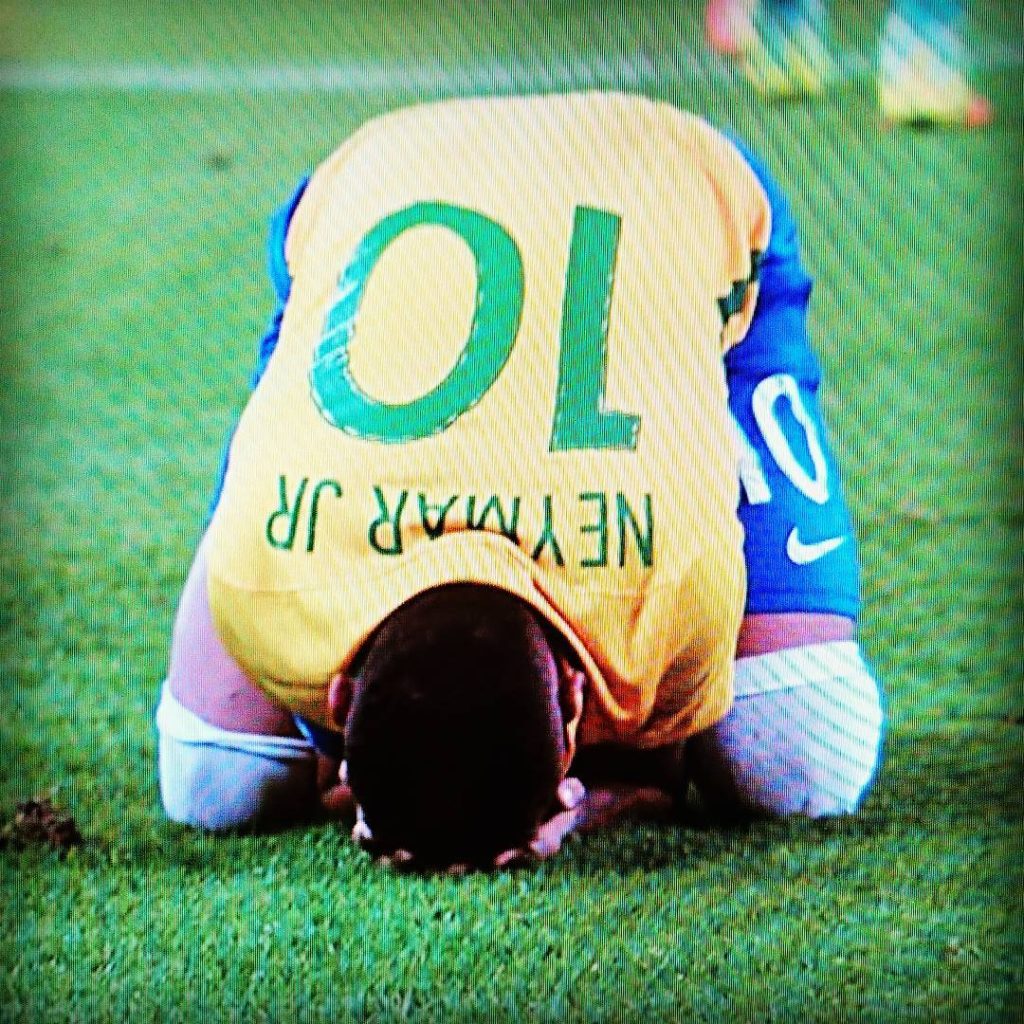大量のメールに、愛は込められるか?
ライブドアの堀江貴文社長は、1日5000通のメールを読んでいるそうだ。しかも8時間寝ている!
こういう人は例外かと思っていたら、最近はそうでもないみたいで「月曜にパソコンを立ち上げるとスパムメールが1000通くらい来てるのよねー」と涼しげに言う人が身近にいた。インターネット関連の仕事をしている女性だが、要は、1日に処理するメール量が違うのだろう。
彼女のような人にメールを出す場合、タイトルは英文にしてはいけない。というような基本的なことも「メール道」を読むとよくわかる。じゃあ、どういうのがいいタイトルなのか? 本書には具体的で示唆に富んだ実例が満載されており、送信者名の設定から電子署名、返信を加速する方法、「礼儀正しさ」と「親しみやすさ」のバランスまで、ビジネスメールの書き方を手とり足とり教えてくれる。だが、最も重視されているのは、そんなふうに量産されるメールに「いかに心を込めるか?」ということだ。
著者は、親しい人へのメールは「こんにちは! くめです!」と、ひらがなで元気に始めるという。しかも「こ」と入力するだけで、いくつかのバリエーション(漢字バージョンとか肩書き付きバージョンとか)に変換されるのだ。私は思わず笑ってしまったが、ここは笑うところではない。「変換と同時に、頭の中で『こんにちは!』と復唱すると、一文字一文字打ったのと同様に心が込もるような気がいたします」と著者はいう。大真面目なのだ。
結びの言葉も、相手との関係や内容に応じて10種類ほどを使い分けて単語登録をしているそう。「しかしながら、本音をいえば、こうした大切なあいさつを、いわば手抜きで入力、変換することに、ささやかな罪の意識を感じています。一字ずつ打つのに比べて、心が込もらなくなるような気もするのです」。そこで著者は、表示されるあいさつ文を「目で追って、心で復唱」するのである。
極めるべき「メール道」は、各々の職業やキャラクターやメール量によって変わってくるだろう。私自身は本書に書かれていることをほとんど実践していないことがよくわかったし、今後も実践しないような気がする。だが、ゲーム感覚でラクしてボロ儲け!というトーンにあふれたネットビジネス界において、著者の説く「道」は救いだ。趣味よりも儲かることを仕事にしろと言い、メール速読術を提唱し、ビジネス処理能力を極限まで高めていく志向のライブドア社長とは、対極の立場だと思う。
「メール道」を通じて、豊かな人に近づいていきたいという著者だが、豊かな人の定義は「生活や趣味に困らないだけのほどよい『お金』を持ったうえで、『時間』『友人』『家族』『ライフワーク』『健康』『信条』もバランスよく持っている人」のこと。これは、村上龍が定義する成功者の定義「生活費と充実感を保証する仕事を持ち、かつ信頼出来る小さな共同体を持っている人」(人生における成功者の定義と条件/日本放送出版協会)と通じるものがある。
最後の章のタイトルは「『メール道』の先にある『道』」。メール道はここに行き着くのか!と驚き、ウケた。
私は、たまたま著者にお会いしたことがある。「メール道」も素晴らしいが、実際の人柄のほうがはるかに面白い。とりわけ、しょうもない馬鹿話をする時の生き生きとした表情といったら!
というわけで、大真面目な文体には、つい笑ってしまう私であるが、著者のキャラを思うと、本書は、おそらく笑ってもいい本なんじゃないかと思うのだ。(ちょっと不安)
2004-10-05
amazon