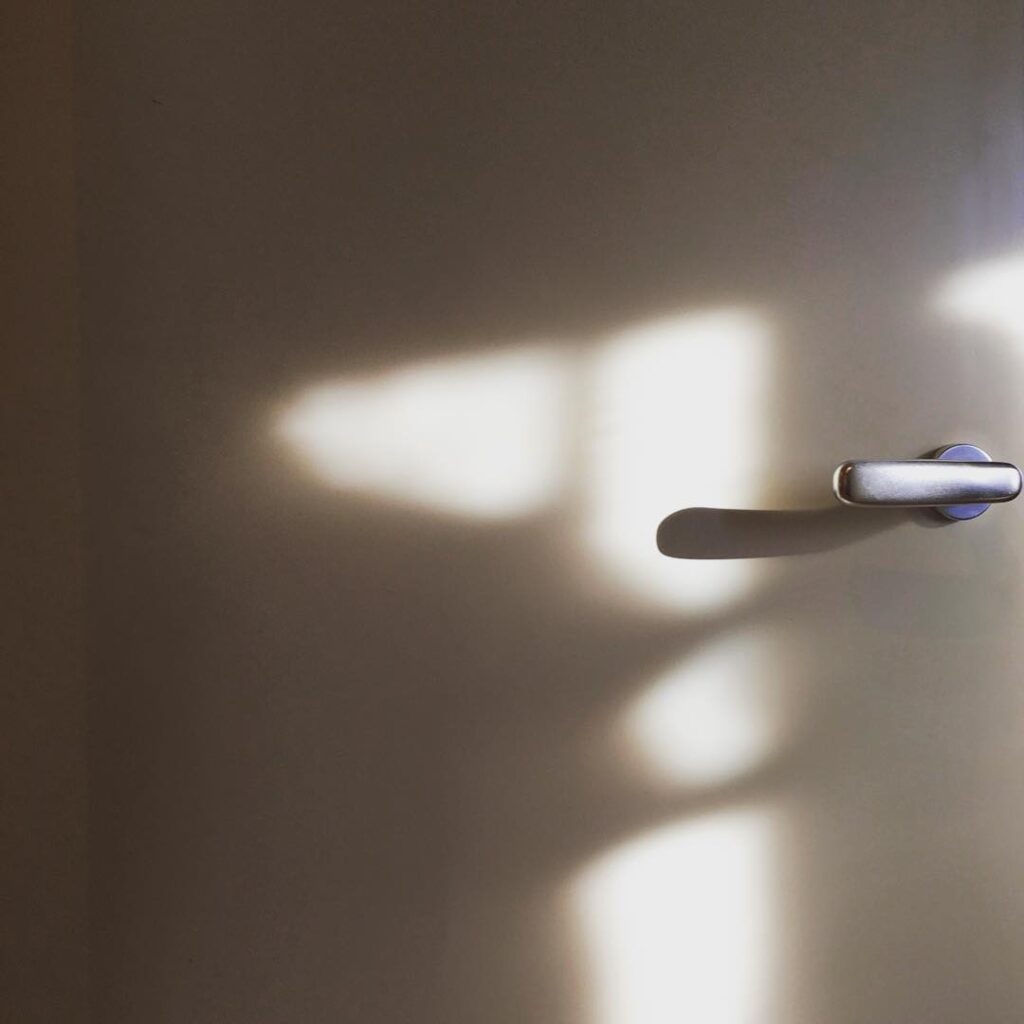いちばん明るいヴィスコンティ映画。
ヴィスコンティ映画祭が終わった。パスポートを手に入れ、毎日のように通った。睡眠時間を削ってでも、見る価値があるものばかりだった。匂いや温度や倦怠までがリアルに感じられ、イタリア11日間の旅に行ったような気分になった。
イタリアン・ロードムービーの原点であり処女作の「郵便配達は二度ベルを鳴らす」(1943)、若き甥(アラン・ドロン)に負けない初老の男(バート・ランカスター)の魅力を描き切った貴族映画「山猫」(1963)、ヴィスコンティ映画のあらゆる要素がミステリアスに凝縮された「熊座の淡き星影」(1965)、マストロヤンニとアンナ・カリーナが不思議な日常を演じた「異邦人」(1967)、三島由紀夫も絶賛した死の美学が暴走する「地獄に堕ちた勇者ども」(1969)、徹底した視線への執着が美しい「べニスに死す」(1971)、不倫の顛末を完璧なカラーコーディネートで見せた遺作「イノセント」(1976)etc…。
おしゃれな短編もある。舞台裏の女優の魅力が炸裂する「アンナ・マニャーニ」(1953)、貴族階級の労働とファッションをテーマにした「前金」(1962)、キッチュなメイクアップ映画「疲れ切った魔女」(1967)の3本だ。
ヴィスコンティ映画の真骨頂は、何と言っても、崩壊寸前のダメ男の美学。ほとんどの作品にダメ男が登場するが、女との対決という意味では、リリカルなナレーションがそそる究極のメロドラマ「夏の嵐」(1954)のダメ男ぶりがいちばん抜けている。経済力のある女がダメ男に金を与えれば、ダメ男はその金で若い女を買ったり、飲んだくれたりして、さらにダメになっちゃうのであるという経済論理がここまで正面きった女への侮辱や罵倒とともに語られた映画があっただろうか。女というものは、わかっていながらダメ男に何度でも騙されるし、騙されたいのである。ダメ男を信じたいからではなく、自分を信じたいからだ。愚かな女は結局、ダメ男によって完膚無きまでに打ちのめされるのだが、それでも「夏の嵐」の女は最後まで負けない。すべてをさらけ出すダメ男に対し、究極の愛のムチを選択するのである。「イノセント」と同様、凄まじい結末だ。ダメ男の名を呼びながら、気がふれたように暗い街を彷徨う女の姿が忘れられない…。
だが、最高の1本を選べといわれたら「揺れる大地」(1948)だろう。上映後、熟年カップルが「暗い映画だねー」と悪態をつきながらそそくさと会場をあとにするのを見た。シチリアの貧しい漁村を、現地住民を使い、現地ロケで撮ったモノクロ映画なのだ。この作品で不幸に見舞われ、崩壊してゆくのは、貴族ではなく庶民の一家なのだから、設定は確かに暗い。だけど中身は、最も希望に満ちた映画だと思う。主人公はまだ若いし、密輸業者と共に島を出て行った弟の今後も楽しみだ。
南部からミラノへ移住した一家の苦労を描いた「若者のすべて」(1960)では、南部の様子が描かれないため、アラン・ドロン演じる三男が最後まで故郷に固執する理由がわからなかったのだが、「揺れる大地」を見てようやく理解できた。人は、自分が生まれ育った土地の仕事や環境を不遇と感じたとき、それでも故郷に執着すべきなのか? それとも外の世界へ出て行くべきなのか?
「揺れる大地」は、外へ出て行かない映画なのに、希望がある。小さな漁村の中に、世界がある。自分にとって最も重要なものは何かを考えれば、どんな悩みにも自ずと答えは出るはずで、そこに愛と信念がある限り、人は何度でもやり直せるのだと思う。たとえどん底に陥っても、自分の原点と可能性を見つめ直して、もう一度、這い上がろうとすればいいのである。
2004-10-19