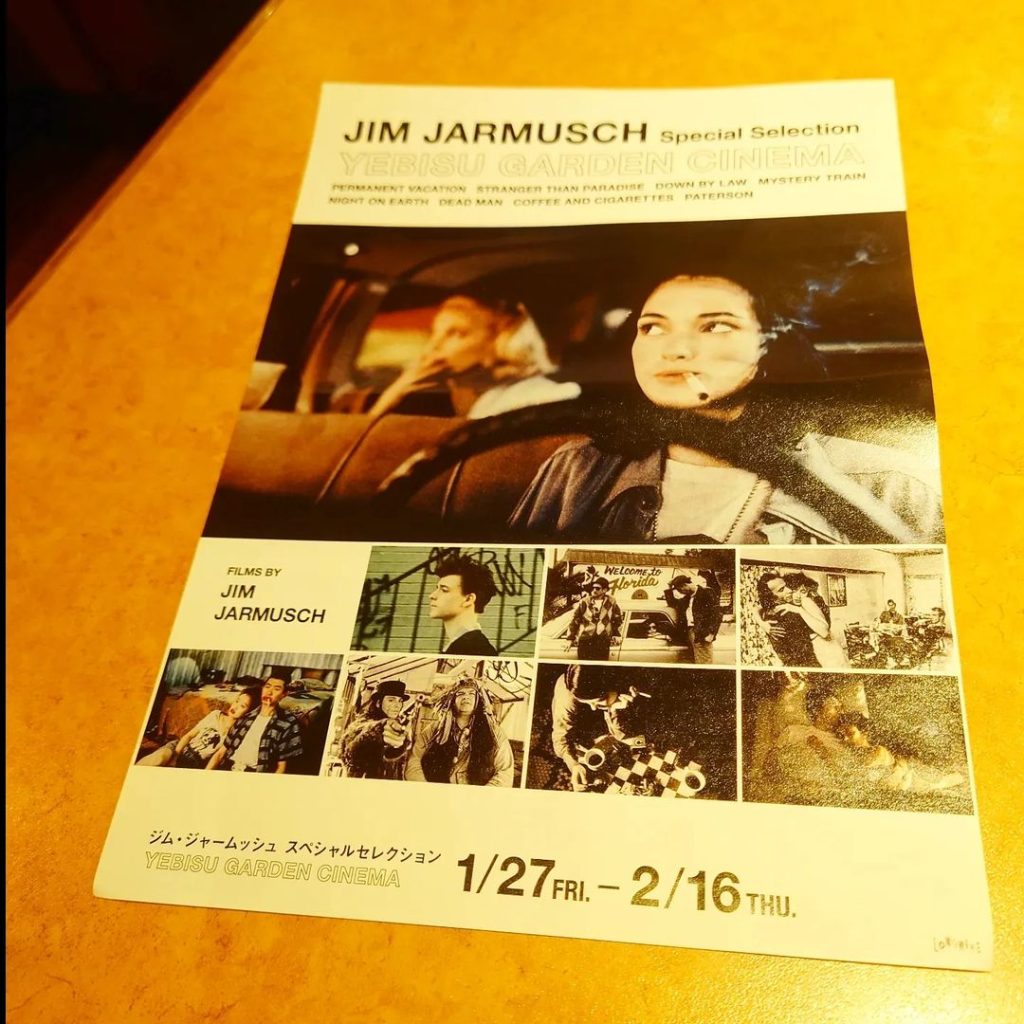愛が恋に変わるとき。
今年惜しくも106歳で亡くなったオリヴェイラ監督が、2010年、101歳のときにカンヌ国際映画祭<ある視点>部門のオープニングを飾った『アンジェリカの微笑み(The Strange Case of Angelica)』が、ようやく日本で公開された。監督は1952年、この脚本の第一稿を書いたという。どんな時代に見ても変わらないであろうシンプルな強度をもった作品で、世界はいつだって、まっさらな気持ちで撮り直すことができるのだと思った。舞台は、世界遺産に登録されている歴史あるポートワインの産地だ。
死を扱いながら、これほど嬉しくて楽しくて美しい映画があるだろうか。繋がりたくないものとばかり繋がってしまいがちな現代において、どこにも繋がらずに繋がりたいものと繋がれるこの映画はユートピア。死んでいるはずのアンジェリカの表情は笑っちゃうほど魅力的だし、死者を死者らしくない真逆のベクトルで描いてしまうオリヴェイラは、やっぱり天才。
アンジェリカは、結婚したばかりで亡くなった名家の娘。彼女の母は、娘の最後の姿を写真に残したいと望む。撮影依頼のため、執事が夜遅く写真店に行くが、店主はポルトへ出かけて留守だった。最近この町にやって来た写真好きな青年がいるよという通りすがりの男の一言で、イザクの下宿のドアがノックされることになる。
時代設定は現代だが、電話もスマホもデジカメも使わない。イザクは双眼鏡で外を眺め、鍬でぶどう畑を耕す農夫を見つけると、朝食も食べずに写真を撮りに行くような男だ。撮影に使うのはもちろんフィルム。下宿の女主人は、謎めいたイザクを気にかけているが、トラクターの時代に鍬の作業を撮るなんてと、半ば呆れている。
アンジェリカと対峙したイザクは、時代遅れの農夫たちにカメラを向けるのと同じ気持ちで、彼女を撮ったのだろうか。彼が撮影すると、アンジェリカは目を開けて微笑む。彼の「愛」は通じたということだ。だが、死者に微笑まれるという究極の不意討ちをくらった彼は混乱し、結果的に、本気で「恋」に落ちてしまうのだ。
撮影の前、カトリックの修道女であるアンジェリカの妹が、明らかにユダヤ人の名前とわかるイザクに不安を抱くシーンが心に残る。イザクは、信仰の違いなど気にしないと言い、妹を安心させるのだ。アンジェリカの写真は、親族とのそんなささやかな交流の末に撮られたものであり、このとき既に、イザクはアンジェリカを微笑ませていたのかもしれない。
愛しい娘を失った母は彼女の写真を求め、憔悴した夫は彼女の墓を離れない。故人の何に執着するかは人それぞれだ。写真を撮ったイザクは、やがて彼女の生身を求め始める。イザクとアンジェリカは、シャガールの「街の上で」という絵みたいに、夢の中で抱き合って浮遊する。
物語の鍵となる小鳥の死をきっかけに、イザクが走り出すシーンは斬新だ。地上に目的などないはずだから、彼は目的なく走っている。おかしくなっちゃったのね、と言われながら美しいレグアの町を一途に走る滑稽さが、胸を突く。
「アンジェーリカー!」(ジェにアクセント)と叫ぶイザクの声が耳から離れない。愛しい人の名を呼ぶのはコミュニケーションの基本だから、彼はおかしくなったわけじゃないし、願いはちゃんと叶う。私たちは過去や死者、既に終わってしまったように見える考えにとりつかれ、夢中になることもできるのだ。なんて美しいんだろう。そして、何もこわいものはない。
2015-12-12