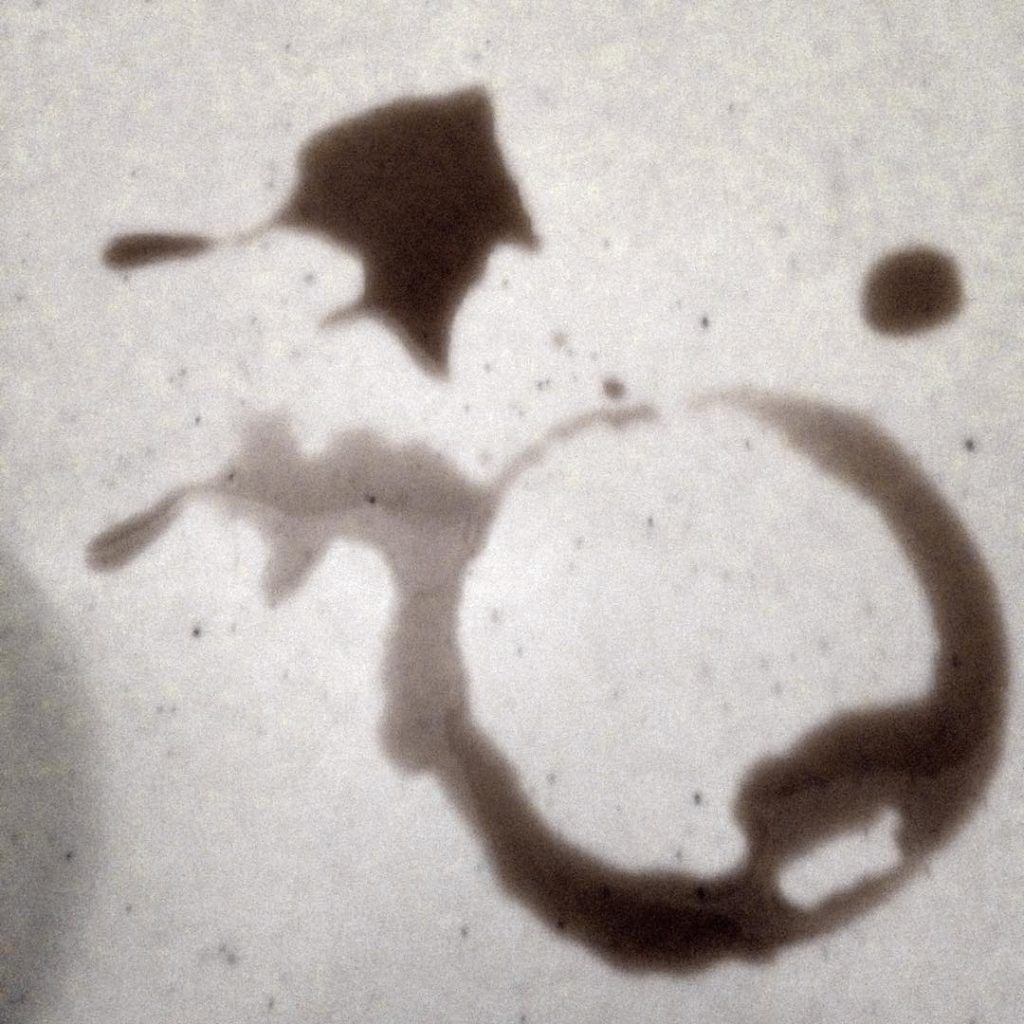ヒッピーガールが修道女を演じたら、こうなった。
シンプルで硬質なのに、リリカルで鮮烈。1962年のポーランドを舞台にしたロードムービーであり音楽映画。
修道院で育った戦争孤児のアンナは18歳。修道誓願の時期が来たが、シスタ一から一度も面会に来ない肉親の存在を知らされ、修道女になる前に会ってきなさいと勧められる。アンナは外界に出て、唯一の肉親である叔母のヴァンダを訪ねる。
自分がユダヤ人で、本名がイーダであることを知るアンナ。ヴァンダと共に両親が戦時中に住んでいた家を目指すが、実はヴァンダもあるものを探している。それらを見つけることで、2 人の人生は大きく変わっていく。
ヴァンダはエキセントリックな検察官。酒を飲みながら白のヴァルトブルクを運転し、恋愛を投げやりに楽しみ、強面でやや壊れてもいる。こんな魅力的な女と4日間も一緒にいたら、イーダが影響を受けてしまうではないか。修道女の誓いを立てる前の、最初で最後の旅なのに。
イーダの硬さは簡単には崩れず、髪にはベールを被ったままだが、きっかけはファッションより前に、音楽が連れてくる。宿泊中のホテルの階下から聞こえてくるのはコルトレーンの「ネイマ」。なんて罪深く甘美なのだろう。兵役を逃れながら放浪しアルトサックスを吹くイケメンは、昼間ヴァンダの車をヒッチハイクし、ホテルまで一緒に来た男。舞台装置は完璧だ。
音楽という名の空気は、いつだって壁を越え、ピンポイントでターゲットの耳に囁く。国境や文化や言葉をすり抜ける突破力と、無関心な層には決して届かない選別力をもって。もしもイーダの心に響く音楽がロックだったら、ボサノバだったら、違う展開になっていたはず。音楽の趣味は人生を揺るがす。
イーダの場合、とりあえず初めて出会った男がそれほど悪い奴じゃなくてよかった。しかし彼女は、彼と人生を共にしようなんて思わない。初めて自由を知った彼女は、彼と生きる人生を自由とは思わないのだ。「アナと雪の女王」で13年ぶりに外界と接触し、他国の王子とあっさり恋に落ちてしまうアナとは格が違うのである。
イーダが鏡の前でベールを取り、髪をはらりとほどくシーンは「アナと雪の女王」でエルサが髪をふりほどき雪の女王に変身するシーンを思わせるが、そこにはエルサのような自己肯定の開放感はない。ポーランドとアメリカは違うし、1962年と現代は違う。イーダは自由を垣間見た瞬間に、その限界を悟っただろう。
髪を見せ、ハイヒールをはき、ドレスをまとい、酒を飲み、タバコを吸い、踊り、恋愛をすることはなんて楽しくて簡単なんだろう。なんて軽くて柔らかくて儚いんだろう。そうイーダは思ったはずなのだ。誰でもできることで状況を変えるのは難しい。柔らかさに流れるのは簡単だけど、イーダの武器は硬質さ。それを棄てない限り、彼女はたくましく生きていけるだろう。
音楽もなく規律正しい修道院での食事の時間にイーダは笑う。外界を知ってしまったら、自分だけが生き残った理由を知ってしまったら、もう他の修道女たちとは同じでいられない。彼女が今後どういう選択をしていくのか楽しみだが、イーダを演じたアガタ・チュシェブホフスカが、今後女優を続けるかどうかも興味深い(続けるつもりはないと言っているが)。
監督が「演技経験が一度もなく、演じたいとすら思っていない女の子」を探す中で主役に抜擢された彼女の第一印象は、イーダ役にはまるで似つかわしくない娘。「むやみに飾り立てたヘアスタイル、古臭い服、ウルトラクールな物腰の、人目をひくヒッピー」だったそうだ。
ヴァンダを演じたのはアガタ・クレシャという有名な女優だが、その強烈なキャラクターは、監督が慕っていた老婦人がモデル。煙草を吸い、酒を飲み、冗談を言う温かく寛大な彼女が、20代後半の頃、冷酷で狂信的なスターリン主義の検察官だったと知ったとき、ショックを受けたらしい。「このパラドックスは、何年もの間脳裏を去ることがありませんでした」と言う。
事実は想像を超え、妄想に貢献する。
2014-8-7