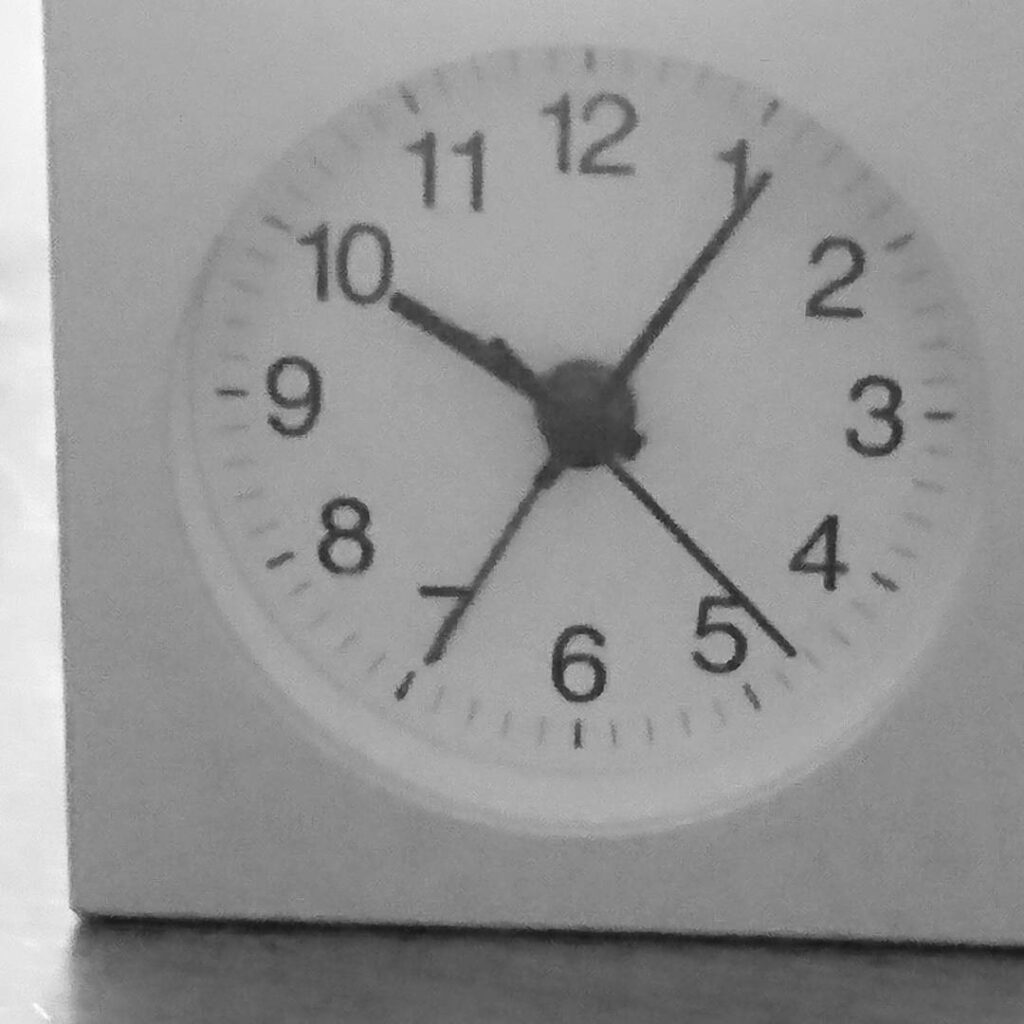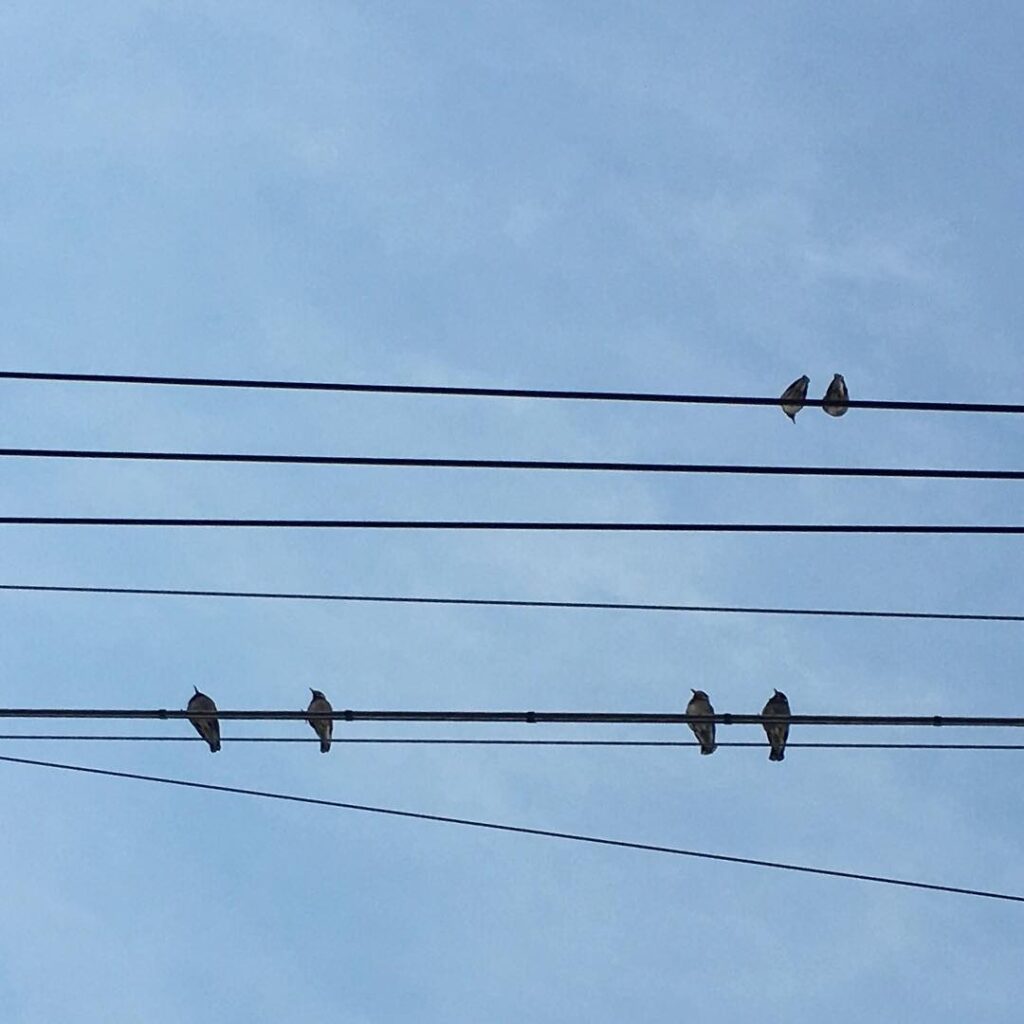美術品とランチ、どっちが大切?
「社員食堂潜入ルポ」というのを雑誌でやったことがある。メーカーや商社やデパートやテレビ局や官庁の社員食堂に何とかして潜り込み、ランチを食べ、施設や人を観察し、会話を盗み聞きするというたわいないものだ。私がそんな企画を持ち込んだのは、公式のアポ取材に疲れていたからだった。広報担当者に時間を割いてもらったり、資料を用意してもらったり、あれこれ食べさせてもらったりしたら、勝手なことなんて100%書けなくなるに決まってる。
この映画を見て思い出したのは、大組織を無断で内部から眺めたそんな日々のことだった。ニコラ・フィリベール監督は当初、記録フィルムを撮るために1日だけルーヴル美術館に呼ばれたそうだが「これは映画になる」とひらめき、翌日も翌々日も通いつめてしまったという。無許可で撮影していても誰にもとがめられず、正式に許可を取ったのは3週間後。迷路のように入り組んだ巨大な建物の中では、少人数の撮影クルーなんて目立たないくらいバラエティに富んだ職種の人々が働いているのである。はたしてルーヴルは、懐が広く寛大なのだろうか?それとも、あまりの大組織のため無神経で危機管理が甘いのだろうか?
この映画は、ルーヴルの美術品ではなく、そこで働く人々にスポットをあてた企業CMのような作品だ。美術品を運ぶ人、展示する人、ディレクションする人、修復する人、掃除する人、電話受付する人、料理する人などの日常が映し出され、上映終了後の映画館は、口々に感想を述べ合う声でいっぱいになった。職場の同僚を誘うには最適なデート映画かもしれない。どこの会社でも「株式会社***の秘密」という映画を撮ればいいのに。インナー向けのCMとして、これほど面白く、働く人の士気を高めるものはないと思う。
学芸員の一人は、監視員たちにこんなことを言う。「モナ・リザとミロのヴィーナスを同じ部屋に展示すれば観光客は満足するだろうが、私は展示数を増やし選択肢を広げたい。ルーヴルとは繰り返し参照すべき巨大な書物なのだ」と。
ゴダールの「はなればなれに」(1964)の中に、ルーヴルを全速力で駆け抜け、最速鑑賞記録に挑戦する皮肉っぽいシーンがあるが、私もルーヴルを訪れた時は、夥しい数の作品があらゆる場所にゴロゴロと無造作に配置されているのを横目で見ながら、モナ・リザとミロとニケの間を駆け抜けた。でも、今になって思うのは、そういうボリューム感の印象こそがルーヴルの手触りで、海外から借りた作品を神経質に展示せざるを得なかったり、コレクションの目玉として「ヘアリボンの少女」を6億円で買っちゃったりする日本の美術館とは対照的な「リッチさ」に衝撃を受けたのも事実。略奪品があまりにも多すぎるのだ。多くはナポレオンが得た戦利品だから、ウィーン会議でずいぶん返却されたらしいけど。
ルーヴルの「リッチさ」の印象は、映画を見ても同じ。日々の雑務の背景としての美術品は意外と大胆に扱われており、何十年ぶりに倉庫から出した大作も、カビが生えていれば「残念だわ」とあっさり削られてしまう。
どんな会社にも、自社の製品やサービスを愛している人とそうでもない人がいるわけで、ルーヴルで働くスタッフの中には、膨大な美術品に愛着のない人もいることだろう。実際、映画の中で職員たちがもっとも生き生きとして見えるのは、イヴ・サンローランがデザインした新しい制服を試着するシーンや、社員食堂で何を食べようか品定めしているシーンなのだった。
*1990年 フランス
*上映中
2004-01-22