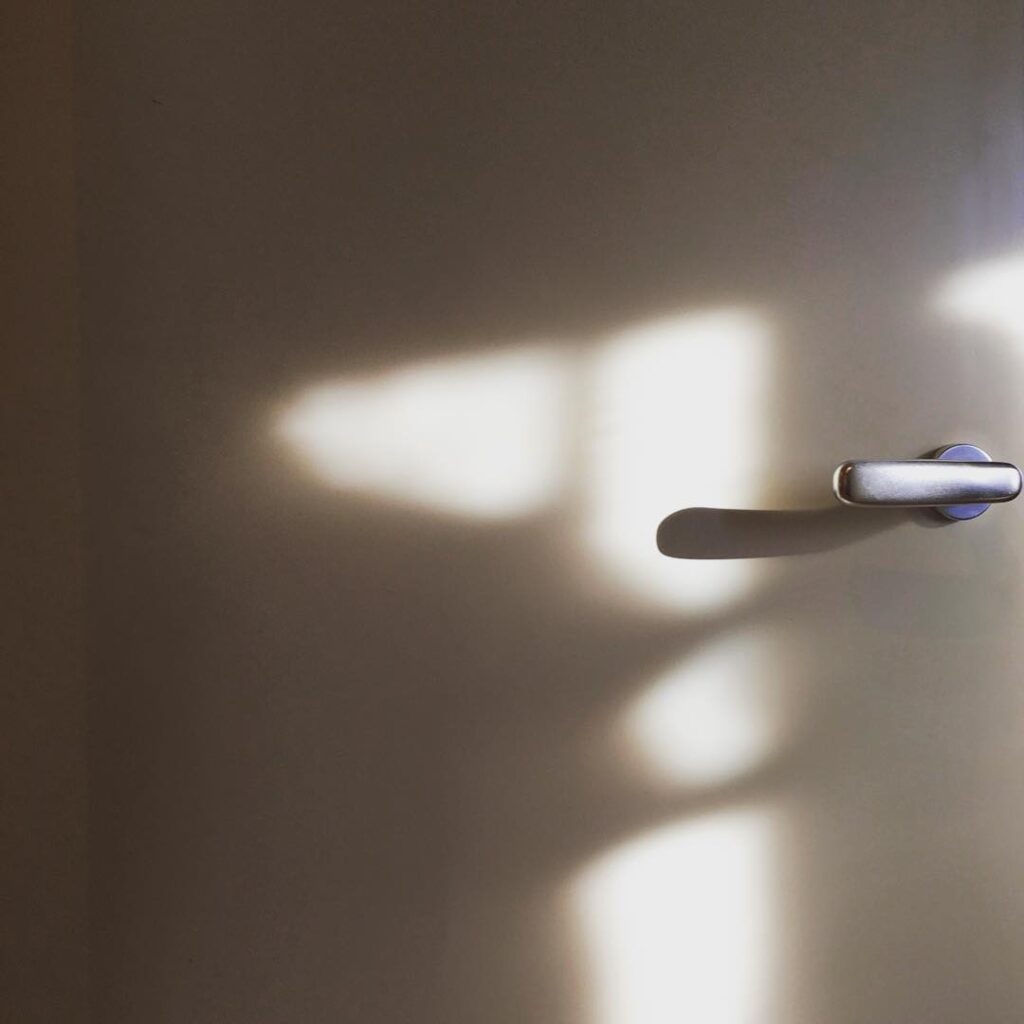「不自由な映画」と「自由な写真」。
年齢を重ねても不器用な人は多い。この映画は、そんな生き方にスポットを当てた。かっこいいとこなんてないし、夢のようなことも起こらない。6人の男女が織り成すダサダサの恋愛映画。
とりわけ不器用なのが、パン屋で働いているのに何度もパンをひっくり返し、いつも髪が乱れていたりスカートがめくれていたりする問題解決能力のない女オリンピア。とても他人ごととは思えず痛い! 不器用な人をなめるんじゃないわよ、と言いたいところだが、映画の撮り方自体も不器用なので、まあいいかって感じ。
不器用な人がこの映画を見ても救われないし解放感もない。ベネチアまで行ってもロードムービー感すら漂わない。彼らが仲間とだけコミュニケーションしているからだ。牧師が「僕にはもう必要ない」とかいってマセラッティを手放すってのも、あまりに紋切り型。
この映画全体を貫く不自由さの理由は、ラース・フォントリアーを中心としたデンマークの4人の監督たちによる「ドグマ」のルールに従っているからかもしれない。許されているのは手持ちカメラを使ったロケーション撮影のみ。小道具やセットを持ち込んではならず、背景以外の音楽を使ってはならず、カラーでなければならず、人工照明は禁止。殺人や武器の使用、表面的なアクションも禁止…一体、何のためにこんな制約を? 1ミリも理解できない。
私は、この映画を見るために新宿へ行ったわけだが、photographers’galleryで開かれていた蔵真墨の写真展とセットにしたのは正解だった。
蔵真墨の写真は私だ―多くの人がそう感じると思う。女子高生やらビジネスマンやらおばさんやらおっさんやら多様な人物が写っているのに、圧倒的なシンパシーへと導かれる。美しいものを美しいとくくらず、不器用な人間を不器用とくくらないクールな客観性。ステレオタイプからの限りない自由。そこから生まれるエッジイな笑い。人+場所+瞬間の吸引力。それは、デンマークとイタリアで撮影された映画にすら欠けていたロードムービー感だと思う。
こういう写真は、偶然には撮れないはず。「普通の人」のキャスティングのセンスが素晴らしすぎるし、ほとんど正面から撮ってるし。一体どうやって仕込んでいるんだろう? それだけが知りたかった。だから、ギャラリーの事務所にいたフェミニンな女性が本人であることを知り、私は歓喜した。彼女の写真はなんと偶然の産物なのだそう。「いろいろ問題もあるんですけど」とミステリアスに微笑む彼女。ああ、それらの問題がいかなるものであってもオッケーです、あなたなら。
蔵真墨さんの写真に出会った「Photographers’gallery press」(No.3 1,600)は、仕事柄「コマーシャル・フォト」ばかり見ている私にとって、久々にエキサイティングなアート写真雑誌だった。
たとえば、小津安二郎が1937年に撮った静物写真の強さ。
たとえば、六本木の地下鉄の階段を上がったら目の前に交通安全ポスターがあり「おっとという感じでインパクトを受けて、よしこれ撮っちゃおう」というノリで森山大道が撮った「アクシデント」シリーズ(1969)が、他人の写真を勝手に撮って卑怯だとか、汚いとか、そういうことでいいのかなどと言われたというエピソード。
たとえば、肺がんに侵された肺と正常な肺を並べてあるような脅迫的な写真の場合、どちらがきれいかは趣味の問題であって「ただれた肺をきれいだとかバロック的な肺だとか言ってもいいんじゃないか」というようなことを主張する島田雅彦。
真実に肉薄しようとするカメラマンを揶揄したしりあがり寿のマンガ「キャメラマン・シャッ太」も秀逸!
2004-05-29