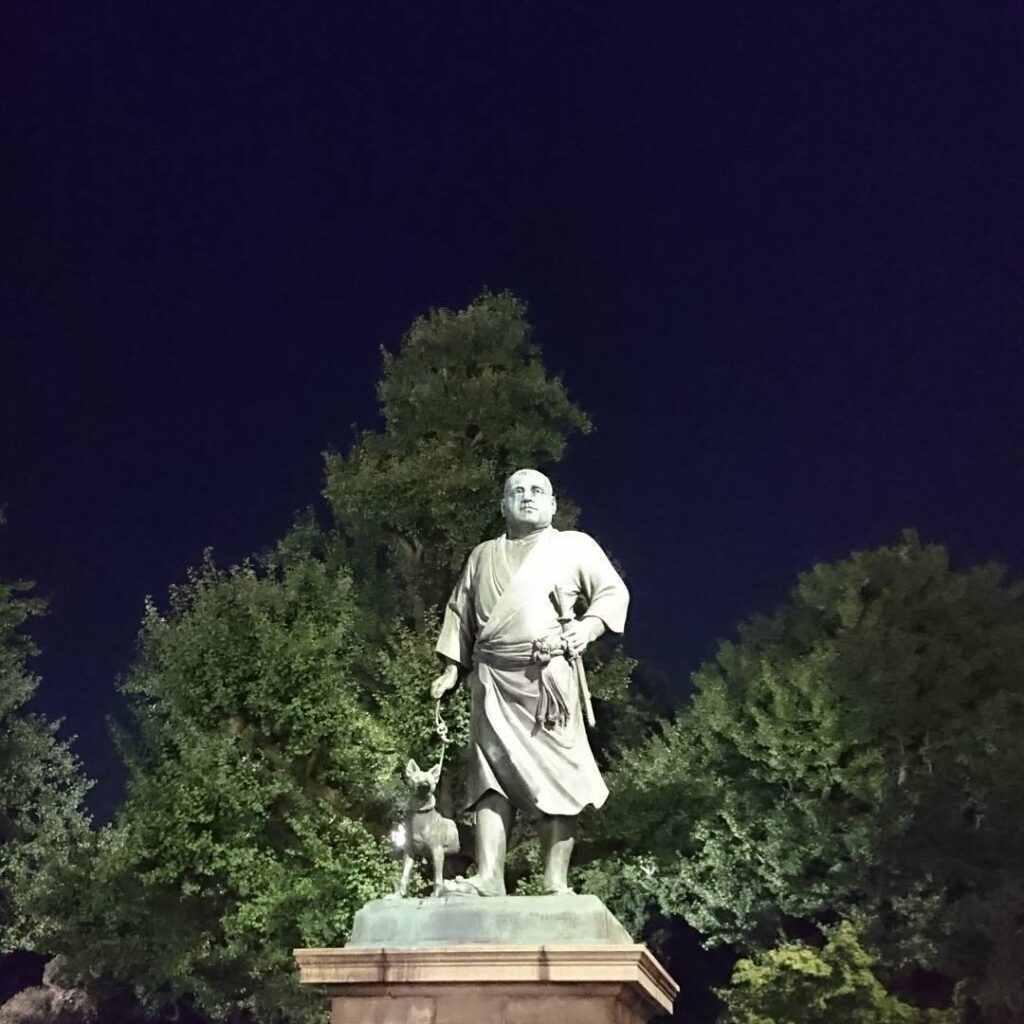超能力で、子供を育てる。
ベーチェット病により27歳で失明した著者は、白い杖を使う一人歩行には自信がもてなかったものの、ひそかに大きな夢を抱いていた。
「それはお母さんになりたいということでした。あるとき、夫の幸治さんに話してみました。幸治さんも、三歳のときに失明した視覚障害者です。『それはいい。ぼくたちに子供ができるなんて、すてきだ!』答える声もはずみます。そして夢は、私たち二人のものになりました」
そ、そんな簡単なことなの!? これはもう、おとぎ話の世界である。著者は、目の見えるお母さんのように子育てをしたいという一心で、大の「犬嫌い」にもかかわらず、盲導犬の力を借りようと決意。アイメイト協会で黒のラブラドール種のメス、ベルナと出会い、一緒に厳しい訓練を受け、一緒に子育てをスタートするのだ。
ものすごくシンプルである。前向きである。生きていく上でのさまざまな困難を、私たちはどんなふうに克服していけばいいのだろうか?などという問いを、この本はことごとく無効にしてしまう。だって、答えはひとつ。できることをやればいいってことなのだから。おとぎ話に、悩みや逡巡は不要なのです。
著者が語るのは、目の見えない生活の苦労ではなく、子育ての苦労でもない。ただ、ひたすらベルナのこと。視線を自在に移動し、しばしばベルナの視点から自分や家族の姿を描いてみせる。著者はなぜ、これほどまでにベルナを愛し、ベルナの目になりきることができたのか? その理由は、たぶん、犬嫌いだったから。出会ったときの抵抗感が大きいほど、つきあっていくプロセスの中で価値観を揺さぶられるほど、相手に対する愛と信頼は大きくなる。一目ぼれの恋愛が、意外と長続きしないことが多いのとは対照的に。
盲導犬とは、盲人を助ける犬のことで、盲導犬を飼うとは、犬に助けられて生きることなのだと思っていた。だが、本書を読むと、盲導犬を飼うとは、実は犬と助け合って生きることなのだとわかる。著者は、毎日のベルナの世話はもちろん、老いたベルナが白内障を患い階段の昇り降りも困難になったとき「最悪の場合自分が抱きかかえるのを覚悟で」ベルナと外出する。つまり、通常の盲導犬として役立たなくなった後もベルナを手放すことなく最期まで面倒をみるのだが、なぜそんなことができたかというと、ベルナのおかげで著者の息子、幹太が立派に育ち、そのころには幹太の目が著者をサポートしてくれるようになったからだ。
見るという行為全体の中で、目が果たす役割は意外と小さいのではないか、と私は思う。著者が決して見ることができなかったはずのベルナの姿を、私たちはリアルに思い描くことができる。人は、たとえ視力を失っても、他人に美しい夢を見せることはできるのだ。
幹太は小学校1年生のとき、クラスの友達や先生の前で「お母さんはボクのことを心の目で育ててくれました」と話したという。彼はその後、どんなふうに成長したのだろう?と勝手に思いをめぐらせていたら、角川書店のホームページに幹太へのインタビューが掲載されていた。
現在の幹太は21歳のジャニーズ系ボーイ。彼は当時、自分の母親の能力を「超能力かなんかの一種」だと思い込んでおり、皆に自慢するつもりで「心の目」という表現をしたということだった。
2002-08-08
amazon