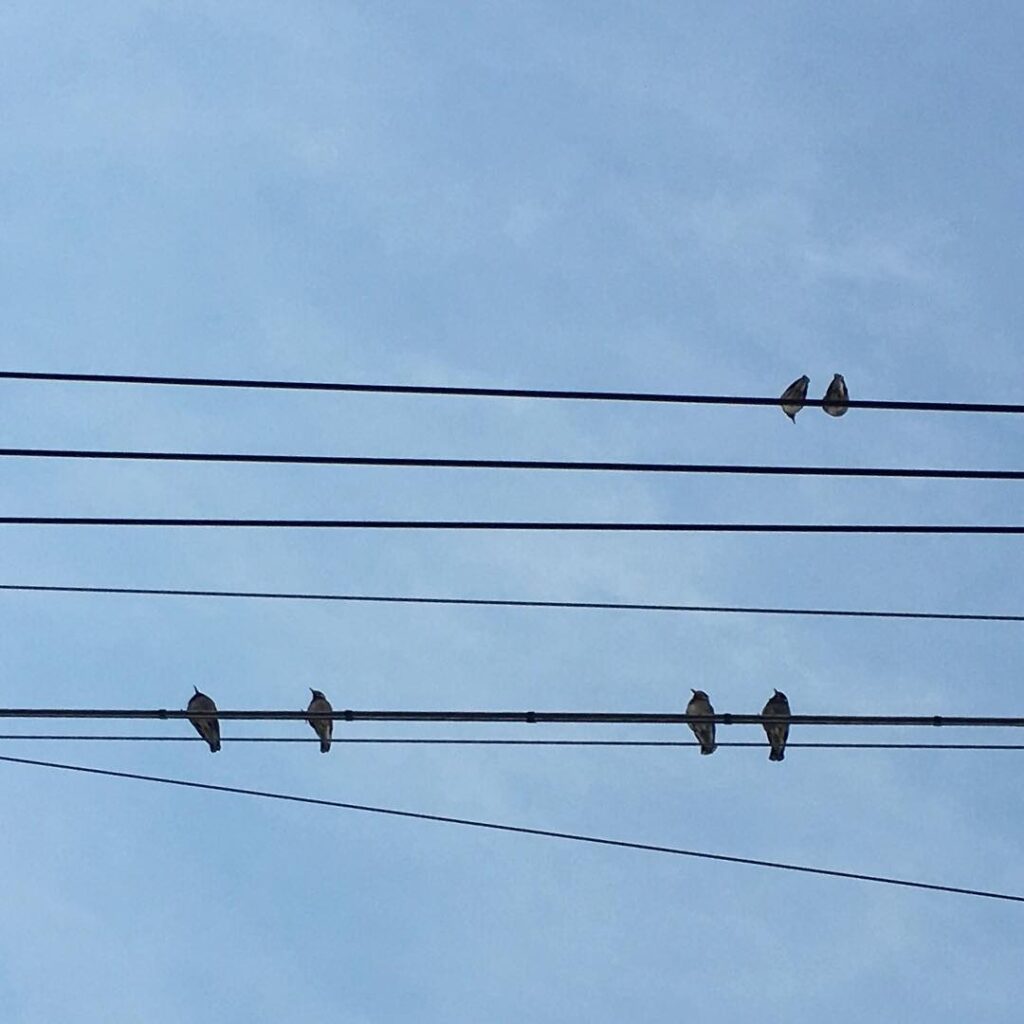1982年の、おしゃれなメロドラマ。
ダニエル・シュミットの回顧上映特集が、アテネフランセ文化センターに引き続き、ユーロスペースでレイトショー開催されている。
中でも「ヘカテ」は「最もファッショナブルな一篇」といわれるだけあって大盛況。日本初公開当時も話題になったようだが、今やその価値はさらに高騰している。北アフリカの風景も、1930~40年代という設定も、昔のクルマも、ディオールオムも、それだけで絵になっている。撮影監督はもちろんレナート・ベルタ。
砂漠の風景に重なる鮮烈なブルーのロゴ、謎の女に人生を狂わされていく外交官、反復される女の後ろ姿、寛大さと諦念の入り混じった滋味あふれるセリフを口にする上司、ふいにレコードを割る男、演劇的に決まりすぎな音楽とセリフと間合い……。でも、この映画で語られるのは、言葉はいつだって無意味だってこと。
モロッコの領事館に赴任した若いフランス人外交官(ベルナール・ジロドー)は、たいした仕事も出世も期待できない中、植民地のエキセントリックな倦怠が渦を巻くパーティで、テラスにたたずむアメリカ女(ローレン・ハットン)と出会う。これはもう、アラン・デュカスがプロデュースするモナコのレストランでイタリア人シェフによるエスニック料理に舌鼓を打つような美味快楽としかいいようがない。実際のところ、マニアックな男やおしゃれな女や知的な老人といった多彩な人種が、たった2回しか上映されない「ヘカテ」を味わうために、週末の夜9時過ぎ、渋谷のラブホテル街に足を運んだのだ。
魔性の女に翻弄される男の話だが、男から見て女がどう見えるのかを、非常に洗練された形で描いている。普通、女のことは、ありえないほどきれいに描くか、どろどろと醜く描くかのどちらかなのに、この監督はどちらでもない。女のことをよく知っているのに、わからないふりができてしまうダニエル・シュミットという男は、正しく女性をリスペクトし、幸せにすることができた人であるはずで、この映画を見れば、魔性の女になって男を狂わせるにはどうしたらいいかがわかる。簡単なことだ。もし、そうありたいと望むのであれば。
映画は回想形式であり、男は結局のところ出世する。女のせいで死んじゃったり殺しちゃったりダメになったりしないのだ。すごくいい話じゃん。このポジティブさ、育ちのよさが、ダニエル・シュミットのセンスのよさだ。フェリーニの「道」なんかとは、格が違うのである。
蓮實重彦の「光をめぐって-映画インタビュー集」(筑摩書房)の中で、ダニエル・シュミットは「映画とは、1秒ごとに24回くり返される現実だ」というゴダールの言葉を受けて、自分はこう言い直したいと語った。
「映画とは、1秒ごとに24回くり返される嘘だ」
そして、こうも言った。
「映画とは、可能な限りの操作によって捏造されるもの」
そう、メロドラマは嘘のかたまりだ。ダニエル・シュミットは、自覚的に、とことん嘘をつく方向で、本質をあらわにする。
2007-02-06