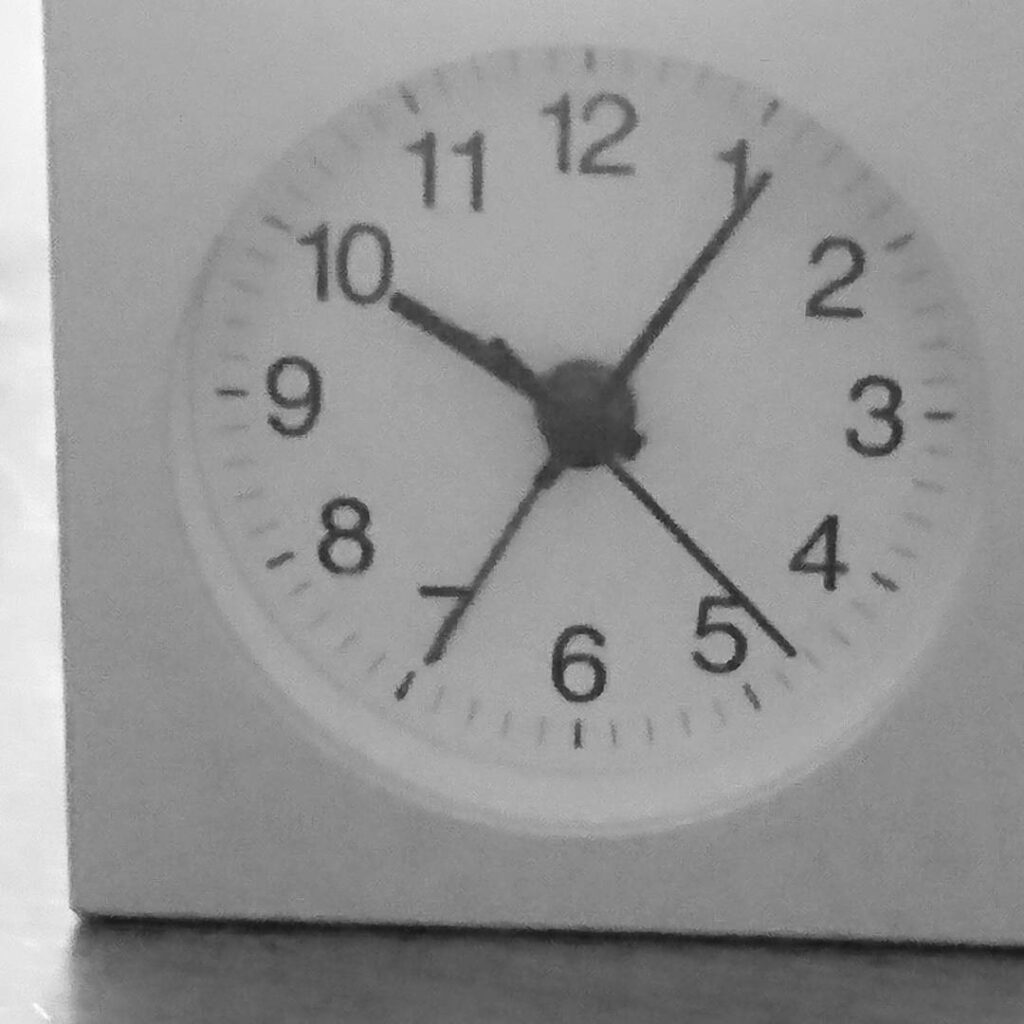彼はまだ、何もしていない。
中国の山西省を舞台に、タオという女性の半生を3部構成で描いた作品。
●過去(1999年-)小学校教師のタオは、羽振りのいい実業家と結婚し、男の子を出産する。男の子はダオラー(=ドル)と名付けられる。
●現在(2014年-)夫婦は離婚し、ダオラーは実業家の父とともに教育環境の整った上海へ。祖父の葬儀でタオのもとに一時帰省した7才以降は、オーストラリアへ移住する。
●未来(2025年-)オーストラリアで学生生活を送るダオラーは中国語を忘れ、母を語らず、先が見えぬまま父に反発するが、あるきっかけで、封印していたタオの名前を口にする。
えー、これで終わり!と叫びそうになった。この驚きは「南へ」という日本語サブタイトルがついていたのに南へ行く前に突然終わってしまったビクトル・エリセの『エル・スール』以来かもしれない。『エル・スール』は、予算の関係で後半が撮影できなかったとも、プロデューサーが後半をカットしてしまったとも聞いたけれど、かなり驚いた。驚きの本当の理由は、大事な部分を描いていないのにも関わらず素晴らしい映画だったことなのだけど。
『山河ノスタルジア』は、物語を始めるにあたっての設定を、美しい映像で、時系列に沿って淡々と描写したに過ぎず、まだ何も始まっていない。登場人物は皆、静かな悲しみを抱えており、これからそこを埋めていく日々が始まるはずなのだ。「愛とは痛みを知ること」という言葉が出てくるが、ここにはまだ、痛みの萌芽しかない。
幼なじみ2人に言い寄られたタオは、炭坑で働く男を選ばず、炭坑を買収した実業家の男と結婚する。離婚した後は、息子の将来を第一に考え、親権を手放す。かつて振った男が身体を病み、困窮していると知れば、ほかに何もできないからと札束をポンと渡す。「愛はお金で買える」を赤裸々に具現化した映画であり、こういうことを1人でサクサク実行していくタオの生命力と、折に触れて流す涙のリアリティに圧倒される。実際、タオが間違っているようには全く見えず、中国という国の底力を見せつけられる思いだ。
だが、経済成長やIT化やグローバル化のひずみは、登場人物一人ひとりの心に蓄積していくのである。近視眼的には見ることができない、そのひずみの正体を、25年(映像としては2時間5分)かけて丁寧にあぶり出し、これは愛の映画になった。
記憶がふいに呼び起こされる瞬間が美しい。どんな些細な過去の片鱗も、葬らずにアップデートしていくことで、かけがえのない未来が開けるのではないかという確かな予感を残して映画は終わる。人生はたぶん、どの瞬間からも、より美しく書き変えることができるのだ。
これからダオラーは、自分のルーツを探す旅に出るだろう。母に再会し、父を理解し、天職を見つけ、愛する人と出会い、初めて父を乗り越えることができるはず。そんなこんなを、あと4時間くらい見ていたかった。ダオラーはまだ、何もしていない。
2016-4-30