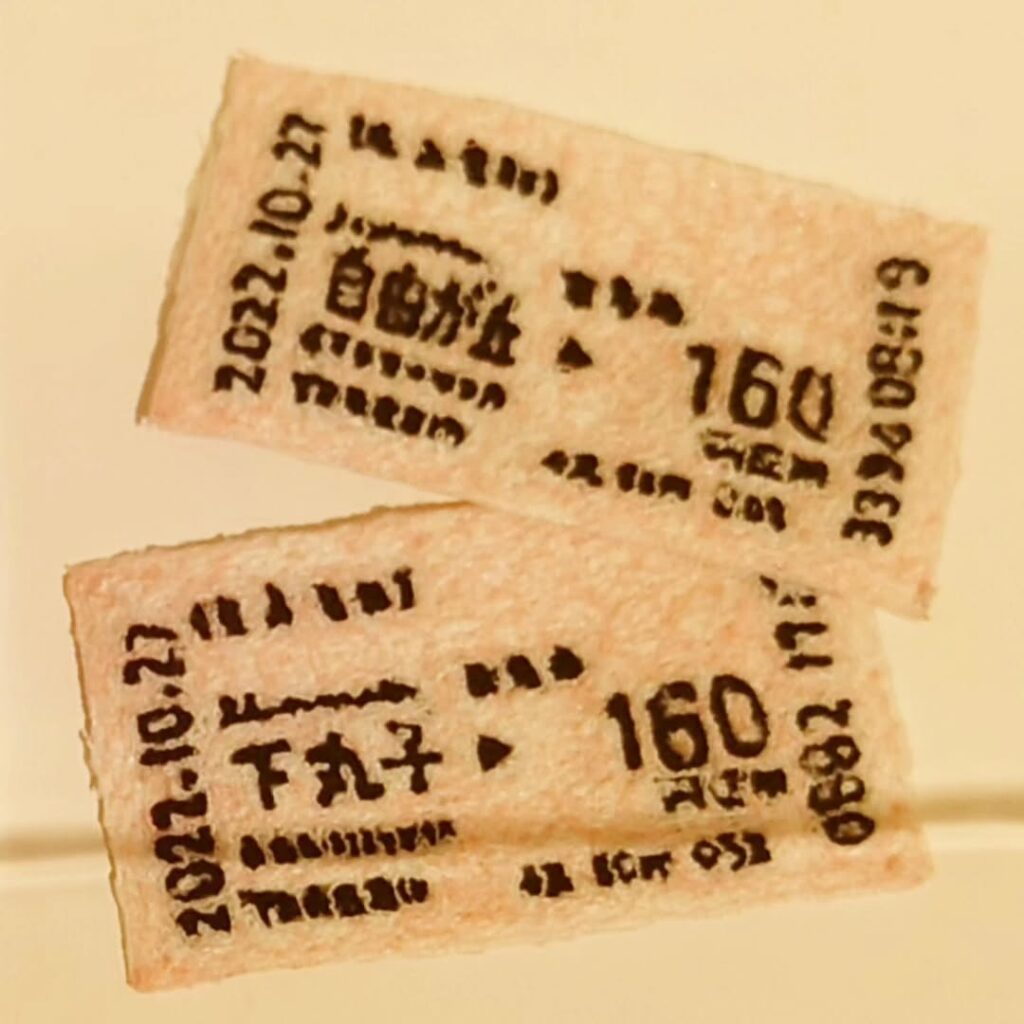みずみずしい毒。
ゲルハルト・リヒター、アンゼルム・キーファーらとともに現代ドイツを代表する画家、ジグマー・ポルケ。日本での個展は今回が初めてだ。「日本におけるドイツ年」ということでようやく実現したわけだが、お金を出したのは日本側。ドイツのいかなる公的機関の助成も受けていないという。「ゲルハルト・リヒター展」(川村記念美術館11/3~)は、デュッセルドルフの州がバックアップしているというのに!
だから、今回のポルケ展は「すべてをカバーできていません。ドイツ人たちがまったく協力的でなかった点は強調しておいてください。オープニングなどになればどうせ彼らはやって来て、自分の手柄のように振る舞うでしょう」(美術手帖11月号インタビューより)ということなのだ。
「不思議の国のアリス」は1971年の作品タイトルで、既成のプリント生地を悪趣味に組み合わせ(2種類の水玉+サッカーのイラストプリント!)、その上にアリスと芋虫と毒キノコ、そしてアリスとは何の関係もないバレーボール選手が落書きのように描かれている。たちの悪い冗談のようだが、いつまでも見ていたい絵だ。なぜ、この作品がポルケ展のサブタイトルに?と考える間もなく、私は既に、自分がアリスの視点でポルケ展を見ていたことに気付く。
ポルケの絵は大きい。これは想定外のことだった。本の中でしか見たことのなかった絵たちが目の前に立ちはだかった瞬間、私は毒キノコを口にしたのである。
大きさも色も、本の中の印象とはまるで違い、別の作品集を見ると、またもや違う。とりわけ紫の顔料を使った3部作「否定的価値」(1982)と、血を思わせる天然の朱砂(水銀と硫黄の化合物)を使った4部作「朱砂」(2005)については、印刷物と実物はまったくの別物!としかいいようがない。2つの作品群は驚くほどフレッシュで、ところどころが濡れたように光っている。会場の温度が上がると、どろどろに溶け出すのかも…。そう、これらは、毒をもりこむように化学変化を想定した色。魔術的な意味を画材にこめるポルケが、錬金術師とよばれる所以である。
21世紀における絵画の意義と役割について、ポルケは控え目に語る。
「絵画があるということはいいことだ、と言っておきましょう。(中略)社会は絵画を必要としていません。社会が求めているのは映像であり、それは今日では機械的に、写真の技術で、フィルムその他によって創り出すことができます。絵画にもう何も啓蒙的なものはありません」
だが、こんなセリフを真に受けてはいけない。真実はいつだって作品の中にあり、実物をみれば一目瞭然なのだから。図録にも収まらず、公的機関のサポート枠にも収まらないポルケは、これからも世の中をあざむき続けるだろう。
*上野の森美術館で開催中(10/30まで)
*国立国際美術館で巡回展(2006年4/18~6/11)
2005-10-28
amazon