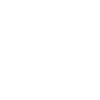必然的に風通しのいい映画。
グ・スーヨン監督はCMディレクターであり、原作本「偶然にも最悪な少年」の著者。
映画化を企画したのはピラミッドフィルムの原田雅弘。
脚本を担当したのはグ監督の弟でコピーライターの具光然(グ・ミツノリ)。
つまりこれ、バリバリにCM業界寄りの映画だ。監督、撮影部、照明部、スタイリスト、ヘアメイクはCMのスタッフで構成されている。とはいえ、それ以外はすべて映画のスタッフだから「映画界のシキタリ」には何度も泣かされたらしい。CMではタレントにいちばん気をつかうが、映画では「監督がとにかく天皇」なのだそう。
グ監督は言う。
「映画では役者たちを俳優部って呼ぶのも興味深かった…CMでタレントは役者というよりも、限りなくモデルに近いからね」
「監督は確かに絵を決める存在だけど、人間的に崇めるのはどっかおかしい…それで閉鎖的だったり、ヘンな緊張感があったり。でも、それって映画の発展を妨げてねぇか。そんなんじゃおもしろいモノはできないよ」
自殺した姉のナナコ(矢沢心)にまだ見ぬ祖国(韓国)を見せたいと思いついたビーボーイのヒデノリ(市原隼人)は、こわれかけた女子高生の由美(中島美嘉)を巻き込み、チーマーのタロー(池内博之)のボロいマークⅡに死体をのせ、4人で東京から博多へ向かう。この単純なストーリーに私はしびれ、期待した。
公開2日目の最終回上映にして7人しか観客のいない品プリシネマではさすがに不安にかられたものの、4人のしょうもない日常が描かれ、ナナコが自殺し、ヒデノリが街をさまようあたりから映画は動き出した。音は浅井健一(SHERBETS)の「Black Jenny」。これはもはやナンニ・モレッティの「親愛なる日記」でパゾリーニが殺された伝説の海岸にヴェスパが辿り着く長回しのバックに流れるキース・ジャレットの「ケルン・コンサート」と同じくらい有無を言わせない。このシーンだけで映画が成立してしまうのである。
その後はピュアなロードムービーだ。死体はどんどん腐るし、お金は調達するしかない。ヒデノリが醸すペラペラな空気感と、媚びも屈託もない由美の存在感が、中味のない言葉や力のない笑いやありがちな心の病いにアクチュアルな輝きを与える。万引きしてもカツアゲしても人を刺しても、特別には悪くない。動物以上、大人以下。そしてKISS。勢いで密航。すべてが自然現象にしか見えない異常さこそが現代のリアル。成長物語にもなってないし、何かが成就するわけでもないけれど、意外とタフで普通な日常が続いていくんだろうってことはわかる。こういう日本の行く末をまじに突き詰めるか、おちゃらけるかの二者択一を迫られるが日本映画のシキタリなのだとしたら、そうではないものをこの映画は見せてくれた。イライラとヘラヘラの間に、こんなにも等身大な道が開けていたとは―
死体に話しかけたり、鼻歌まじりに着替えさせたり、死化粧したりの中島美嘉がいい。CMスタッフによる衣装、メイク、照明、演出が冴え、4人とも演技をしていないように見える。少なくとも「俳優部」の役者には見えない。
「GO」よりも希薄、「ユリイカ」よりも気楽、モンテ・ヘルマンの「断絶」とサム・ペキンパーの「ガルシアの首」とラリー・クラークの「ブリー」を足して3で割って渋谷系にした高品質なB級映画。最悪なんかじゃない。渋谷東映で見れば満席だったはず。きっと。
*全国各地で上映中
2003-09-25