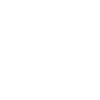映画化という仕事。
はじめに原作を読んだ。
ヒロインのアキが死ぬことは最初からわかっていて、そのことが随所で強調される。朔太郎は、アキに恋する日々の中で突然「どんなに長く生きても、いま以上の幸福は望めない」という「恐ろしい確信」にとらわれてしまう。あまりにもベタな伏線。
が、その後アキが入院し、朔太郎が彼女の自宅に侵入するシーンの鮮やかさといったら。
「自分がすでに彼女を失い、遺品をあらためるために、この部屋に足を踏み入れたような錯覚にとらわれていた。それは奇怪で生々しい錯覚だった。まるで未来を追憶しているようだった」
映画では外されたこのシーンで、小説のテーマが「未来への追憶」そのものであることがわかる。好きになった瞬間に、失うことを恐れなければいけない繊細な季節の物語。アバウトな大人になる前の、理屈っぽく悲観的な思春期の…。
大人になってしまったら「失われた過去」を追憶しても前へ進めない。自分の過去も誰かの過去も、自然に受け入れればいい。それが人を好きになるということだ。現実を太く生きるために。失うことを恐れずにすむように。
2人の現実離れした会話は、小説ならではの気恥ずかしさに満ちているが、映画ではもう少し普通の会話になっており、長澤まさみと森山未來が軽やかに普遍化してみせる。小説には小説の、映画には映画のよさが生きていて、幸福に共存しているのだ。片山恭一いわく「小説のなかで描かれているシーンと、小説にはない映画独自のシーンとが相互に補い合う感じで、決してぶつかっておらず理想的でした」
ウォークマンでカセットテープを聞く柴咲コウがアップになり、彼女の目の色が変化し、涙がひとすじ落ちる。まるでCFみたいなオープニングの表情が、私を釘付けにした。これが女優だ、と思った。限られたシーンで彼女は圧倒的な存在感を見せるのだ。「GO」に引き続き、山崎努の演技もすごかった。どうしてこんなに面白い人物造詣ができるのだろう。
大人になった朔太郎(大沢たかお)が暗い街を走り、その姿が彼に良く似た少年(森山未來)に変わり、高校時代のまぶしい四国の町につながる。クルマなんかなくても、ある風景を駆け抜ければ、映画はロードムービーになる。過去の明るさと現在の暗さの対比、それだけでこの映画は成功している。
いい原作だから、いい肉づけができるのだろうか。俳優の解釈が冴え、表情や走りに凄みが出る。スタッフのリアルが積み重なり、よりピュアなものになる。
映画が面白くなるか、つまらなくなるかの分かれ道について考えた。この映画を見る前に、大好きな監督の、ものすごくつまらない作品をDVDで見てしまったからだ。原作はなく、キャスティングも悪かった。監督の個人的な観念が空回りしていた。
観念を描写に変換し、描写に愛を注ぐ。原作の映画化とは、そういうことだ。何かを何かに変換して納品するのがあらゆる仕事の本質なのだとしたら、自分もそんなふうに仕事をしたいなと思った。右から左へ納品するのではなく、勝手に壊して納品するのでもなく、愛と必然性に基づいた職人的な加工をして納品する。まったく別物でありながら、左右がつながるような。1+1が2以上になるような。
柴咲コウは、原作を泣きながら一気に読み、それがダ・ヴィンチで紹介された。編集担当者はそれを知り、彼女の言葉を小説の帯コピーに使った。行定監督は、原作を愛している女優に頼もうという気持ちで彼女をキャスティングした。まさに愛の連鎖!
女子高生たちが「この映画、まじやばいよ」と言いながら泣いていた。私もそう思う。ウォータープルーフのマスカラでよかった。
2004-06-20