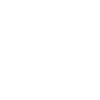南青山で、透明人間になる。
耳の聴こえない夫婦の家を訪問し、インタビューしたことがある。
いちばん鮮烈だったのは彼らの赤ん坊で、母親に抱かれながらも、何か要求があるたびに彼女の体をバシバシたたき、強引に自分のほうを向かせる。夜中もそうやって母親を起こすのだという。泣く前に、たたく。それが、泣き声の通用しない世界における、彼のサバイバル法なのだ。
真っ暗な空間を歩き、視覚以外の感覚でさまざまな体験をする展覧会「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」が南青山で開催中と知り、思い出したのはそのことだった。見えない世界で、自分は何を頼りに生きていくのだろう? それを知るチャンスだと思った。世界70都市で開催され、既に100万人以上が体験しているらしい。
スニーカーを貸し出され、光るものや音の出るものはすべてロッカーへ。白杖(はくじょう)とアテンドスタッフだけを頼りに、見知らぬ7人と共に会場に入る。
完璧な暗闇だった。最初はこわくて一歩も動けないが、アテンドスタッフがリラックスさせてくれる。水の音や鳥のさえずりが聞こえる森林浴のような演出に救われた。蒸し暑かったり息苦しかったりしたらパニックになるところだ。
アテンドスタッフは視覚障害者。赤外線メガネをかけているわけでもないのに、彼だけが8人の位置を把握しているみたいだ。ダンゴ状態でそろそろと移動する8人をナビゲートしつつ、自分は普通の速度で動きまわり、ディズニーランドのスタッフみたいなトークで楽しませながらガイドしてくれる。すごいなと思った。
揺れるつり橋を渡る。わらを踏みしめる。木がある。街がある。スタジアムがある。改札をくぐる。駅がある。駅の喧騒は怖い。ホームから落ちる人がいる。2人乗りのブランコに乗る。ぬいぐるみにさわる。オレンジの匂いをかぐ。階段を下りる。バーがある。サービススタッフがいる。椅子に案内される。テーブルを囲む。ワインを注文する。グラスについでもらう。「アルコールの匂いだ」と声がする。乾杯する。ひと口飲んでみる。「赤?白?」と隣の人に聞かれる。「赤」と答える。サービススタッフに「正解です」と言われほっとする。
なんでもない手すりや椅子、テーブルの心地よさは驚きであった。人が触れることを想定したプロダクツには、やさしさがあるのだと知った。闇の中では、人とぶつかるのも、それほど嫌ではない。誰ともぶつからないよりは、はるかにましなのだ。
見えない世界で、私はふだんより饒舌になっていた。黙っていると置いていかれるかもしれないし、誰も助けてくれないかもしれない。足を踏まれるかもしれないし、踏んでしまうかもしれない。絶えずしゃべっていることが身を守ることにつながるのだ。そう、私は「見えない人」になったのではなく、誰からも見られることのない「透明人間」になったのだった。だから、しゃべることにした。それが私のサバイバル法だった。だが、他の人は違うかもしれない。全然しゃべらない人もいた。バーでテーブルを囲んでいても、静かな人はそこにいるかどうかもわからず、私は、テーブルの形や座席の配置を最後まで把握できなかった。
会場全体がどんなレイアウトだったのかもわからない。私には、どうしても地図が描けないのだ。だが、描けるという人もいた。会場を明るくしてもう一度歩いてみたいなとその時は思ったが、そんな種明かしはしないほうがいいのかもしれない。何も見えなかったのに、まるで映画のような記憶として思い返すことができる。そのことが単純に面白い。
*完全予約制・9月4日まで開催中
2004-08-26