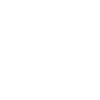映画をつくることは、驚くこと。
ブッシュ前大統領が描いた絵の展覧会がダラスで開かれている。引退後、動物などを描いていたが、地元の画家で大学教授のロジャー・ウィンターに「細部をとらえる力がある。世界の指導者たちを描いてみては?」とすすめられたという。こうして小泉元首相、プーチン大統領、メルケル首相など、彼が関わった人物の肖像画が生まれたのだから、アドバイザーの存在ってすごい。次の展覧会向けには「あなたが関わった世界の殺戮シーンを描いてみては?」とアドバイスしてみてはどうだろう。
『アクト・オブ・キリング(殺人の演技)』は、1965年インドネシアで起きた「残忍なクーデター」に報復する形でおこなわれた「大虐殺」にまつわるドキュメンタリー映画だ。スハルト将軍のもと、100万人希望の市民が「残忍な共産主義者」とみなされ虐殺された。
監督は1974年生まれのアメリカ人だが、インドネシア人の共同監督や協力者たちは、今も命の危険があり匿名だ。監督のモチベーションのひとつは、アメリカがインドネシア軍に死のリストを渡し、武器や資金援助をおこなっていたという事実。インドネシアで幼少時代を過ごしたオバマ大統領は地元のヒーローであり、あるシーンでさりげなく登場する。
監督は当初、虐殺の生存者を撮影していたため軍に阻止された。続行できたのは「加害者を撮影してください。きっと自慢げに語るはずですから」という生存者のアドバイスのおかげだ。国民的英雄である加害者たちは、例外なくオープンに殺人を語り、その行為を再現したがったという。監督は彼らに虐殺の再現映画を撮ってもらうことに決め、加害者たちは自分たちを若くかっこよく面白く見せるためのスタイリスト役はもちろん、被害者役まで積極的にこなし、出演した国営テレビでは映画づくりを得意げに語る。彼らにとって、映画は世界的に有名になるチャンスなのだ。
主役のアンワル・コンゴ(72才)は、監督が出会った41番目の加害者だった。20代のころ映画館でダフ屋をやっていた彼は、軍の要請で1000人近くを殺害。大好きなアメリカ映画の憧れのスターを気取り、独自の効率的な方法で殺ったのだと思い出を語る口調は、50年近くが経過した今も屈託がない。その発言の奇異さをどう解釈したらいいのだろう。自分をとりまく状況や価値観や法律が変われば、人はいつだって殺人を犯す可能性があり、その行為を賞賛されれば罪の意識は永遠に生まれないということだ。
この映画の真骨頂は、史実を伝えたことではなく、映画づくりの熱狂をとらえたことだと思う。命がけの撮影は、そこに関わる人を思いがけない地点に連れていく。残虐さこそがコンセプトなのに残虐すぎるという声があがったり、行為とは裏腹の身体反応があらわれたり、カットのタイミングが遅ければ拷問が果てしなくエスカレートしたり。「これは我々の脅威をPRする映像としてとっておいて、映画は撮り直そう」なんてクライアントが広告代理店に言うようなセリフも出てくる。
「できあがった結果に何らかの意味で自分でも驚くことがなければ、映画を作る意味なんてないと思うね。そうでなければ、結果がどうなるか最初からよく分かっていることのために1年も費やすことになる」とフレデリック・ワイズマンも言っている。
アンワルは、完成した映像の一部を幼い孫たちに見せようとする。「残虐すぎるのでは?」という監督のアドバイスにも「たかが映画だ」と、寝ている孫を起こすのだ。自分が被害者役で拷問され、ただならぬ恐怖を感じた場面を「じいちゃん、かわいそうだろ」という感じで。彼は俳優として体験した予想外の感覚を説明できずに、もて余していたのだろう。「被害者の気持ちがわかった」と言うアンワルに「被害者の恐怖はそんなものではなかったのでは?」と監督は冷静に切り返す。
天国をイメージした極彩色の女性たちの踊りやコントみたいな茶番劇のシーンは、虐殺を正当化し癒しを与えるプロパガンダ映像として、アンワルもことのほか気に入ったようだ。そのいかがわしさ、それっぽさに最初は辟易した私も、最後には、ほっとして笑いながら見ていた。だって残虐なシーンよりは、はるかにましだから。このように人は簡単に洗脳されるのかもしれない。残虐なシーンより怖いことだ。
世界で60以上の賞を受賞し、アカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞にノミネートされた。インドネシアではネット上で無料公開され350万回以上ダウンロードされた。
2014-4-29