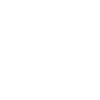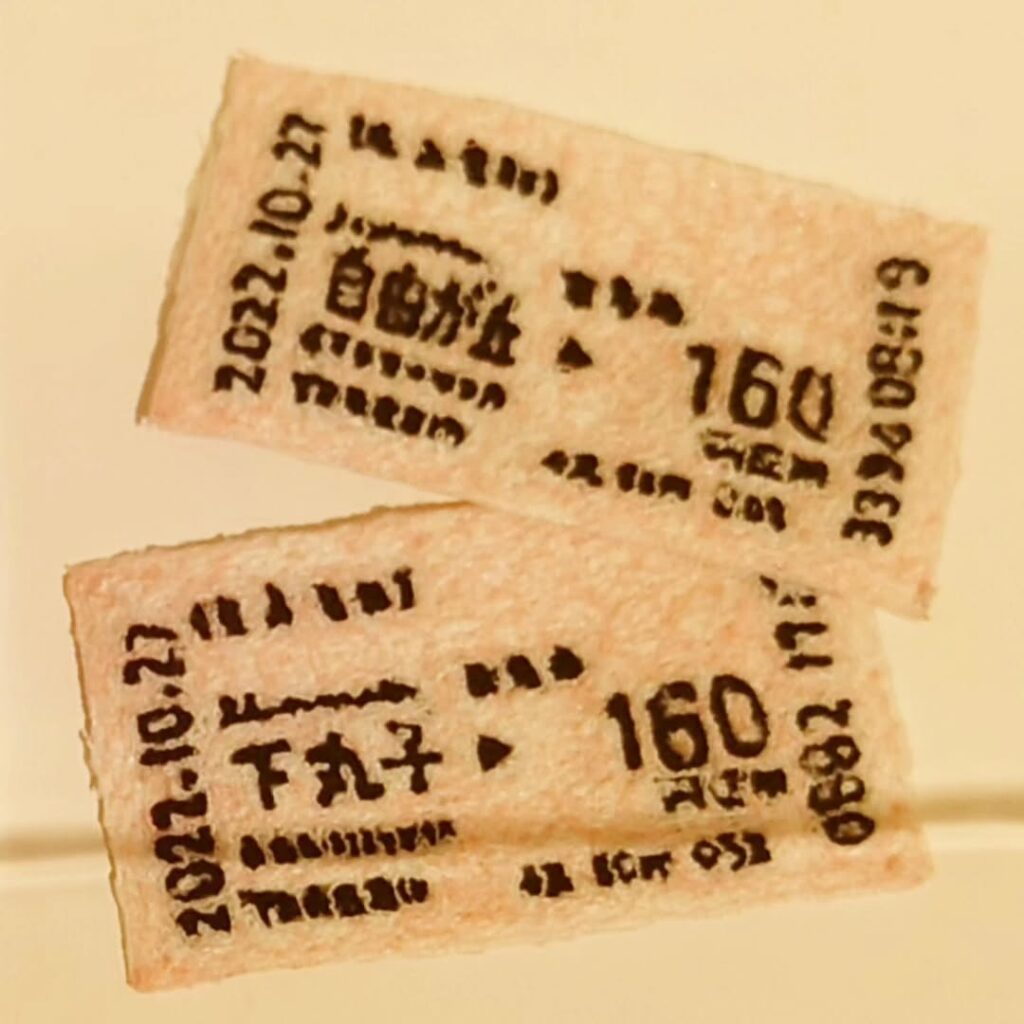記憶は、なぜ美しいのか?
演劇でも、ダンスでもなかった。強いていえば「映像と音と身体による1時間15分間のパフォーマンス」。テーマは「記憶」だ。セリフはないが、パフォーマーがその場で書くメモの内容が、背後のスクリーンに映し出されるなど、全編を通じて言葉に満ちている。
印象的だったのは、書いたばかりのメモを男がちぎって捨てたあと、メモの断片でいっぱいになったゴミ箱を女がひっくり返す行為から始まるシークエンスだ。女の動きにあわせてメモの断片が雪のように舞い、その様子は4つのスクリーンに映し出される。天井からぐるぐるまわりながら床に接近する小さなカメラによってとらえられる映像は、万華鏡のような美しさだ。
言葉の書かれたメモが曖昧な美しいイメージに収斂されていくプロセス。その感動を言葉で表現するのは愚かだろう。目の前で散っていく記憶の断片を、ただただ見守っていたいと切実に思う。
部屋のシークエンスも面白かった。舞台上の部屋と酷似した状況が4つのスクリーンに映し出される。それぞれの時間の流れ方は微妙にずれ、起こるできごとが違うのだ。
小物の色使いや配置はきわめてシンプルで心地よい。だが、複数の似た状況が繰り広げられるにつれ、同じ結末に向かっているというイメージが強調され、不安にかられる。やがて訪問者がドアを開け、部屋の住人に凶器でなぐりかかる….。 それぞれの部屋でヒゲをそったり電話をかける過程が見られるが、結末はすべて「無」だ。つまり、細部の記憶は複数だが、現実はただひとつ。美しくて恐ろしくて洗練された、元も子もないドラマである。
テクノビートのダンスパフォーマンスも見事だった。デジタル映像と有機的な身体のシルエット。その対比だけでスティルフォトとして完成されているのだが、そこに、めくるめくスピード感や空間を引き裂く音響、光と色のパフォーマンスが加わるのだから。パフォーマーの息遣いまで感じられる小さな劇場自体が最新のボディソニック装置となり、至福の「記憶体験」に導いてくれる。
演劇やダンスというジャンルは、「独特の集団臭」や「クライマックスの感動」に辟易させられるケースも多いが、ダムタイプは、最後の舞台挨拶に至るまで何ひとつ過剰なものがなく、不足するものもなく、世界に通用するセンスのよさを感じた。さまざまなジャンルのアーティスト集団なのだと知り、納得した。
*新国立劇場小劇場「THE PIT」にて12月16日まで公演中
2000-12-06