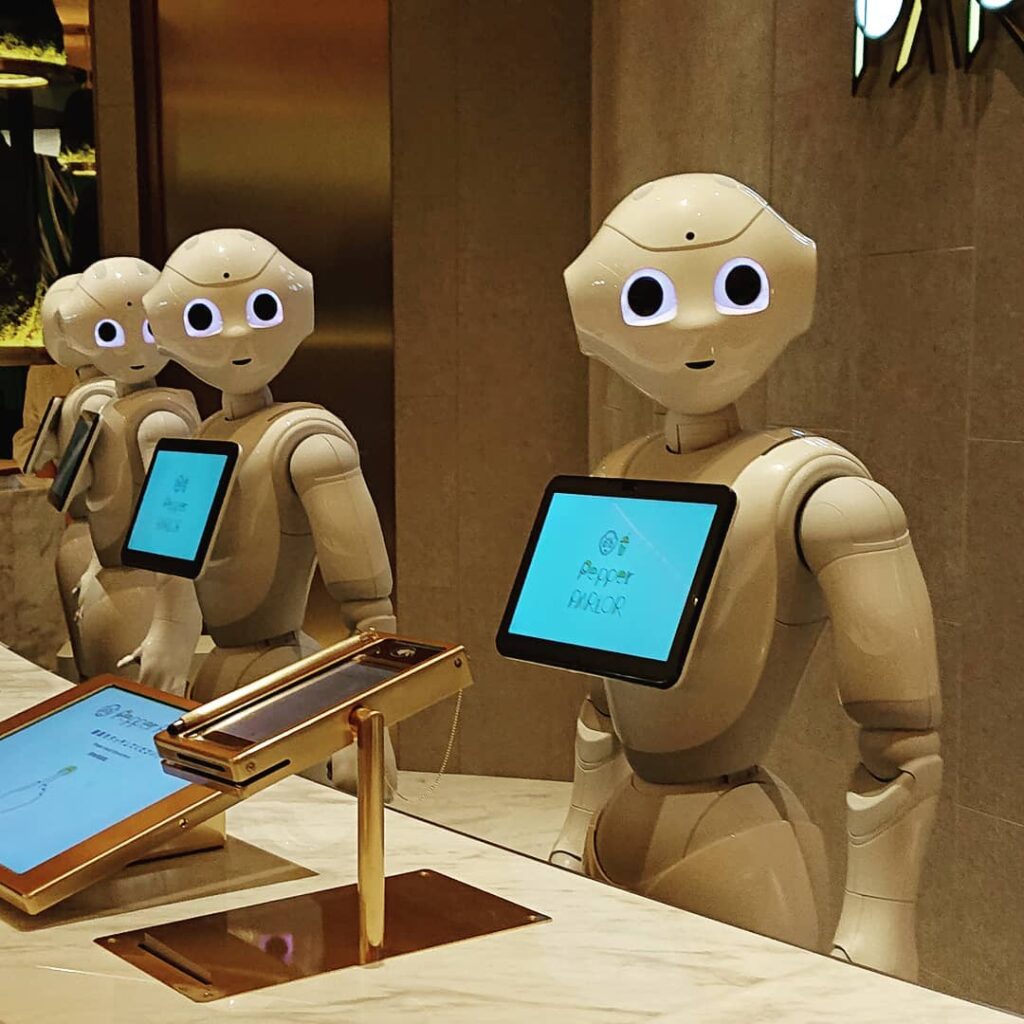真横から目撃した奇跡。
ストーンズの日本公演に関する記事をいくつか読んだけれど、ふーんという感じだった。だが、3月13日の日経新聞夕刊に掲載されていた渋谷陽一のライブレポートは違った。それまで私が読んだ記事には「何も書かれていなかったんだ」と気がついた。
10日の武道館ライブについてのそのレポートを14日夜に読み、いてもたってもいられなくなった私は、15日夜、翌日の東京ドーム公演のチケットを買った。ストーンズのライブに行くのは二度めだし、ロン・ウッドとチャーリー・ワッツはソロで来日したときも見に行ったが、いずれも10年くらい前のことだ。
渋谷陽一はこう書いていた。
「一九九〇年の初来日の時、複数のキーボードで厚く装飾された音に守られて演奏するストーンズに本来のロックらしいグルーヴ(ノリ)は感じられなかった。あのストーンズでさえ、こうして衰弱していくのか、と悲しかったことを覚えている。それから彼らは今回を含め四回来日しているのだが、年々サウンドはシェイプアップされ、グルーヴを増してきた。平均年齢が六十歳になろうとするバンドが年々成長し、グルーヴが若々しくなっていくのだ。あり得ないことだし、ほとんど奇跡といっていい」
私は、ステージの真横に設置された「最後のS席」から「あり得ない奇跡」を目の当たりにした。
1曲目の「ブラウン・シュガー」からアンコールの「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」まで、セットも音も構成もタイトだった。ミック・ジャガーのスレンダーなボディ、腕を前に突き出す独特のポーズ、張りのあるヴォーカル、エネルギッシュな動き、「みんな、どお?」といった日本語に、私は釘付けになった。スプリングコート風のロングジャケットやブライトカラーのシャツやノースリーブのインを自然に脱いだり着たりした。最後はピンクのシャツだ。こんなにシンプルでセンスのいい服を、女の子のようにさらっと着こなし「まねしたい」と思わせてしまう59歳の男が一体どこに?写真や映像で見るよりも、そして10年前よりも、彼は明らかにチャーミングだった。
チャーリー・ワッツのパワーも相当なものだったし、ロン・ウッドは相変わらず少年のように飄々と楽しんでいた。キース・リチャーズのソロは声もかすれており、ギターも最初と要所だけ弾くといった感じだったが、エモーションの伝わり方はただごとではなかった。彼が最前列のファンに近づき、ひざまずいて声援にこたえる姿を見ているだけで、どきどきしてしまう。
正面のスクリーンもまともに見えない位置だったから、生身の彼らを見るしかないし、音だってスピーカーの後ろから聴いているようなものだ。おかげで、ステージの前後の広がりやメンバーたちの「無意識」をバックステージから眺めるような面白さがあった。
私はその夜、1968年にゴダールが撮った「ワン・プラス・ワン(sympathy for the devil )」のビデオを見直してみた。「悪魔を憐れむ歌」ができあがっていくレコーディングのプロセスと、当時の政治状況を彷彿とさせる革命劇を1+1として編集した奇跡的な映画だ。当時の服、クルマ、スタジオのインテリア…すべてが鮮やかな色調で、今見ると「おしゃれでかっこいい映画」としか思えない。
そこには、20代のミックとキースとチャーリーが映っていた。スタジオ風景のほとんどが1シーン1カットで撮られているためか、彼らはカメラを意識しているようには見えず、ごく自然に音合わせをしている。「今日の彼らとほとんど同じじゃん!」と私は思った。
*JAPAN TOUR 2003/3月21日まで
2003-03-18