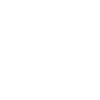文学は、におう。

フランスのパティシエ「ピエール・エルメ」のケーキを初めて食べた感動は忘れられない。美味しい洋菓子の味と言ってしまえばそれまでだが、眠っている脳細胞をくすぐり、遠い記憶を呼び覚ますような「深い味」がした。
私はまだ、衝撃を受けるほど「深い匂い」には出会っていない。パフューマ-(調香師)である著者の「異性のにおい」体験を読んでそう思った。男子校に通っていた17歳の彼は、友人の家に遊びに行った時、友人の姉、弥生さんの部屋をのぞいてしまう。「若い女のにおいと言ってしまえばそれまでだが」と前置きしながら、彼はその部屋の匂いを描写する。
「シーツの上に投げだされたしなやかな肢体のような掛け布団の姿と肌触りのよさそうなパジャマから漂う肌のようなにおいと、シャンプーの香りなのか化粧品なのか、髪の毛のにおいのようでもあるなんとも女っぽい香りがまざりあった、心地よい、からだから力の抜けていきそうなにおいであった」
彼はその日から弥生さんに恋をするが、面識のない彼女への思いは胸にしまい込むよりほかなかったという。実際に会えたのはずっと後、友人の結婚式に呼ばれた時のこと。初対面の美しい人妻に彼は何を感じたか? これはもう短編小説の世界である。
以前ブームとなった「ブルセラ」についても、匂いのプロによる考察は深い。下着を売る女子高生とそれを買う男たちの間に横たわる「エロスと匂いをめぐる意識のズレ」が暴かれ、身体やセクシュアリティにおける匂いの位置づけの曖昧さが指摘される。匂いそのものが抑圧されてきた近代社会では「『芳香』を例外的にポジティブなものと設定しつつ、それ以外のあらゆるにおいを『悪臭』と一括して排除することで、思考の対象から外してきた」のだ。香料の起源は媚薬であり、媚薬の原型は体臭であるにもかかわらず、体臭を消すことに躍起になり、再び香料を振りかける矛盾に本書は切り込んでいく。
「色即是臭、臭即是色、すなわち、エロスは匂いであり、匂いはエロスである」という当たり前の事実に気づかせてくれるのが「匂いフェチ」「下着フェチ」「ラバリスト」たち。彼らの行為はフェティッシュと匂いが不可分の関係にあることを証明する。
匂いと香りの違いは大きいと私は思う。ワインやアロマテラピーでは、悪臭を含む「匂い」という言葉よりも、芳香のみを意味する「香り」という言葉が好まれる。匂いに執着するのは変態だが、香りに執着するのはお洒落なのだ!あからさまに匂いを嗅ぐことがマナー違反とされる社会において、心ゆくまで香りを堪能できる趣味が隆盛である事実は興味深い。赤ワインの「動物臭」や「なめし皮の香り」に凝り出したら、もはやフェチ以外の何者でもないと思うのだけど。
老人向けの売春宿を舞台にした川端康成の小説「眠れる美女」は、セラーで眠っているワインのように、睡眠薬を飲まされて眠っている若い女を嗅ぎ分ける話だ。本書では、この小説が詳細に読み解かれる。「エロスと匂いについて、ここまで透徹した小説を私は他に知らない」と著者は言うが、エロスと匂いについて、ここまで透徹した分析を私は他に知らない。
著者は、弥生さんの部屋の匂いを今も思い浮かべることができるという。
「そのにおいを嗅ぐことを想像するだけで、なんとも胸のうちがくすぐったくなるような切なさと同時に、今でははっきりとエロティックなものとわかるある種の心地よさを覚える。あのにおいは、そのとき引き起こした私の胸のうちのざわめきの記憶まで含めて、決して消え去ることはないのである」
*著者からメッセージをいただきました。Thank you!
2002-03-13
amazon