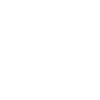かっこいい母の息子はマザコンか?
現在bk1ランキング1位の「世界がもし100人の村だったら」(マガジンハウス)の中に、こんな記述がある。
「もしもあなたが いやがらせや逮捕や拷問や死を恐れずに 信仰や信条、良心に従って なにかをし、ものが言えるなら そうではない48人より恵まれています」
誰かが、ほかの誰かよりも恵まれているなんて、第三者にどうやって決めることができるのだろう?
大雑把なたとえ話を断定形で語るのは、私たちに安っぽい優越感を与えてくれるため?
それとも、読み手にこれ以上考えることを止めさせるため?
「知識の民主化を装った大規模な思考破壊工作」という言葉を私は思い出す。蓮見重彦が以前「ソフィーの世界」(日本放送出版協会)を評し、そう書いていた。
芥川賞受賞作「猛スピードで母は」の主人公「慎」は、第三者にどう思われようが、恵まれている。そのことが主観的に書かれているからだ。母子家庭、いじめ、母の恋愛、失恋、祖母の死、祖父の看病など、ある意味でハードな経験を重ねる慎だが、男勝りでかっこよくて知的な母のもとに生まれたおかげで、ぜんぜん動じないよっていう話。控えめながら圧倒的な優越感に貫かれている。
状況への決定権や選択権のない不安定な小学生時代がナイーブに表現されるが、約20年前を回想するというスタイルだから、痛みは穏やかだし悪人も出てこない。安全圏から過去を反芻する気持ちのいい小説なのだ。どんなできごとも等質であり、水が流れるように淡々と描かれていく。
「母がサッカーゴールの前で両手を広げ立っている様を慎はなぜか想像した。PKの瞬間のゴールキーパーを。PKのルールはもとよりゴールキーパーには圧倒的に不利だ。想像の中の母は、慎がなにかの偶然や不運な事故で窓枠の手すりを滑り落ちてしまったとしても決して悔やむまいとはじめから決めているのだ」
慎の母親自慢は、こんなふうに、子離れできない現代の母親への批判にもなっている。この親子は考え方が似ており、慎自身も、母と母の恋人によって置き去りにされそうになったとき、状況をきちんと受け入れるのだ。ほどよい距離をクールに保つ母と息子の姿は、教育的で示唆に富んでいる。
この小説を村上龍はこう選評していた。
「状況をサバイバルしようと無自覚に努力する母と子を描いた」
「一人で子どもを産み、一人で子どもを育てている多くの女性が、この作品によって勇気を得るだろう」
「社会に必要とされる小説だ」
一方、石原慎太郎の選評は冷たい。
「こんな程度の作品を読んで誰がどう心を動かされるというのだろうか」
積極的に人の心をつかんで揺さぶっちゃうような小説ではなく、必要な人がそこから勝手に学んだり考えたりする、道徳の教科書のような作品なのだと思う。
ただ、いくら距離を保っているとはいえ、小学校高学年の息子が、自分の母親をこんなにも容認し、自慢し、かしずくっていうのはどうよ? マザコン度はかえって高いような気がするのだが。
慎は20年後(つまり現在)、母親の運転手にでもなっていそうで、ちょっとこわい。
2002-02-22
amazon