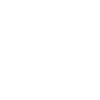不倫とは、罪悪感のこと。
成人男女の約半数が「不倫を許容している」と元旦付けの朝日新聞が発表したのは98年のこと。今は一体どうなっているんだろう? お正月の紙面をにぎわすポピュラー感と「不倫」という言葉の間には、深い深い溝があるように感じたものだが、この映画を見て、今さらのように私は膝をたたいた。クレーヴの奥方のような生き方を不倫というのだ、と。私たちの周囲に満ちあふれている不倫は、その内容がいかにヘビーであろうとも、「遊び」とか「浮気」とか「本気」とか「家庭外恋愛」とか「たまたま結婚してるだけ」とか・・・とにかくそういう軽い感じの言葉が似合う。
17世紀のフランス文学を映画化した作品だが、宮廷世界を現代の上流階級に置きかえたところが面白い。オリヴェイラ監督は92歳にして挑戦的。 単なる古典的な映画ではないのだ。
キアラ・マストロヤンニ(カトリーヌ・ドヌーヴとマルチェッロ・マストロヤンニの娘)演じる「クレーヴの奥方」が恋する相手はロック・スター(ペドロ・アブルニョーザというポルトガルの現役ロック・アーティスト)。 二人が惹かれ合っているのは明らかだが、彼女は彼を避け続ける。 「人気スターならもうちょっとましなアプローチの方法があるんじゃないの?少なくともサングラスは外さなくちゃ。ちょっと笑わせてみせるとかさー」。 そんな客席の感慨をよそに、彼女の美しい表情はくずされぬまま、指一本ふれない恋愛が展開されていく。しかし、このもどかしさこそが重要で、ああ、これがまさしく不倫なのだと私は理解した。何もしていないのに罪悪感にさいなまれるほど、情熱を燃やすってこと。心の中であっさり許容、妥協してしまうような行為は、不倫とはいえないのかもしれない。
こんな思いを妻に打ち明けられたクレーヴ氏は病んでしまい、「そこら辺の男みたいに、だまされていたかった」みたいなことまで言う。それはそうだろう。行動的には彼女は潔白であり、「あなたよりも好きな人がいるけど何もしてない」と正直に告げただけなのだから、だまって浮気しちゃう女よりも、ある意味で残酷。夫は立派すぎる妻に苦悩するのだ。さらに、当のロック歌手や元恋人まで苦しめてしまうのだから、クレーヴの奥方は罪な女だ。
しかし、たとえ何人の男を犠牲にしようとも、二人の間に障害がなくなろうとも、過激なまでに自分の道を貫く彼女。傷ついたり、情熱的な愛が失われてしまうのを恐れているのである。もしも私が彼女の友達だったら、「好きになった人を追いかけないでどうすんのよ?」と肩を揺さぶっちゃうところだが、幸いなことに、彼女が唯一心を打ち明ける幼友達は、温厚な修道女。最初から火に油を注ぐような悪友はいないのである。
偶然が多く、死が多く、設定は不自然だし、ロック・スターもちょっと変。なのに、ため息が出るほど洗練された作品だ。ライブ・シーンを見て、ジョナサン・デミがトーキング・ヘッズを撮った「ストップ・メイキング・センス」を思い出した。あの映画のすごさは、ステージのすべてを撮り、それ以外を撮らなかったことにあると思うが、「クレーヴの奥方」は、主役ではない彼のステージで始まり、彼のステージで終わる。余計な説明や後日談がないところが、かっこいい。
ストーリーや時間の経過は字幕で流し、必要なシーンだけをていねいに描いていく手法。 印象的なカメラワーク、緩急のリズム感、軽快さと重厚さの絶妙なバランスが心地よく、熟成したビンテージ ポートワインのように味わった。
*1999年 ポルトガル=フランス=スペイン合作/銀座テアトルシネマで上映中
2001-06-19