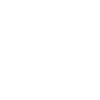殺しと殺しのあいだをどう生きるか?
説明を極力省いたミニマムな描写。最先端テクノロジーを駆使したカルチャー。倒錯したセックス。意味をはく奪された刺激的な暴力行為…。しかし、この短編集のいちばんの特長は、そぎ落とされた文章の中に、不安定で気弱で理性的でどこか懐かしい「普通の感情」がときおり混じることだと思う。それは、涙が枯れ果てたあとの泣きぼくろのようでもあり、荒廃した世界に咲く最後のバラのようでもある。
「今日の、この時代に、セックスに誠実さを求めるなんて、ズレてるってことわかってるけど、でもわたしって理想主義者なんだわきっと」(「ゴム手袋」より)
「よもや人を食うなんてことはなかろう、と。ときどき、自信がなくなるが…」(「ネクロ」より)
「こちらがなにもかも譲歩して、それでいてこのふたりのほっそりとしたパンクスタイルの十代の娘たちが、屈強な成人の男に居心地の悪さを与えるというのはなぜなんだ」(「ストレート・レザー」より)
「そこでパーティはおひらき。あらゆる幻覚が終わらねばならないように。あるいは、そのように人が言うように」(「迷彩服とヤクとビデオテープ」より)
「ストーカー」という短編の中には、こんな一節がある。「殺しだけをしていれば、そいつはすごいことだ。しかし、殺しと殺しのあいだに間がある」。この短編集全体のコンセプトを見事に言い表した文章だ。殺しをやっている間は、皆ハイなのであり、ハイな小説が、私たちをある程度興奮させることは間違いない。ただし、問題は、殺しと殺しのあいだをどうやって生きるかということなのだ。我に返って孤独と向きあったときにこそ、人間の真価が顔を出すし、小説の真価もあらわになる。
この短編集のハイな部分を読んでいると、何がかっこよくて何がかっこ悪いのかわからなくなり、男女の区別や善悪の判断がつかなくなる。ぐちゃぐちゃにされて、あっさり放り出される気分だ。結局、他人のことなんて理解できないし、自分がいつ死ぬかもわからない。そんな結論にたどりつく。
だが、その後、じわじわと勇気がわいてくる。人生短いんだから、いくところまでいってみよう、と。で、その結果、すげえ!という境地に到達したとしても、「ストレートレザー」の主人公のように、「自分のパンツで血を拭きとり、鞄にあったもうひとつのズボンをはいた。黒い「執務用」ズボンだ。注意深くロープを巻き、鞄の中にしまった」というふうに、命ある限りは淡々と目の前の現実を処理し、次の場所へ向かいたい。それが、タフということだと思う。たとえ内面がぼろぼろに崩れ落ちそうになっていたとしても。
*第1回インターネット書評コンテストで最優秀賞をいただきました。ありがとうございました。
2000-12-15
amazon